
【津和野町長選挙】公開質問状への回答を公開します!
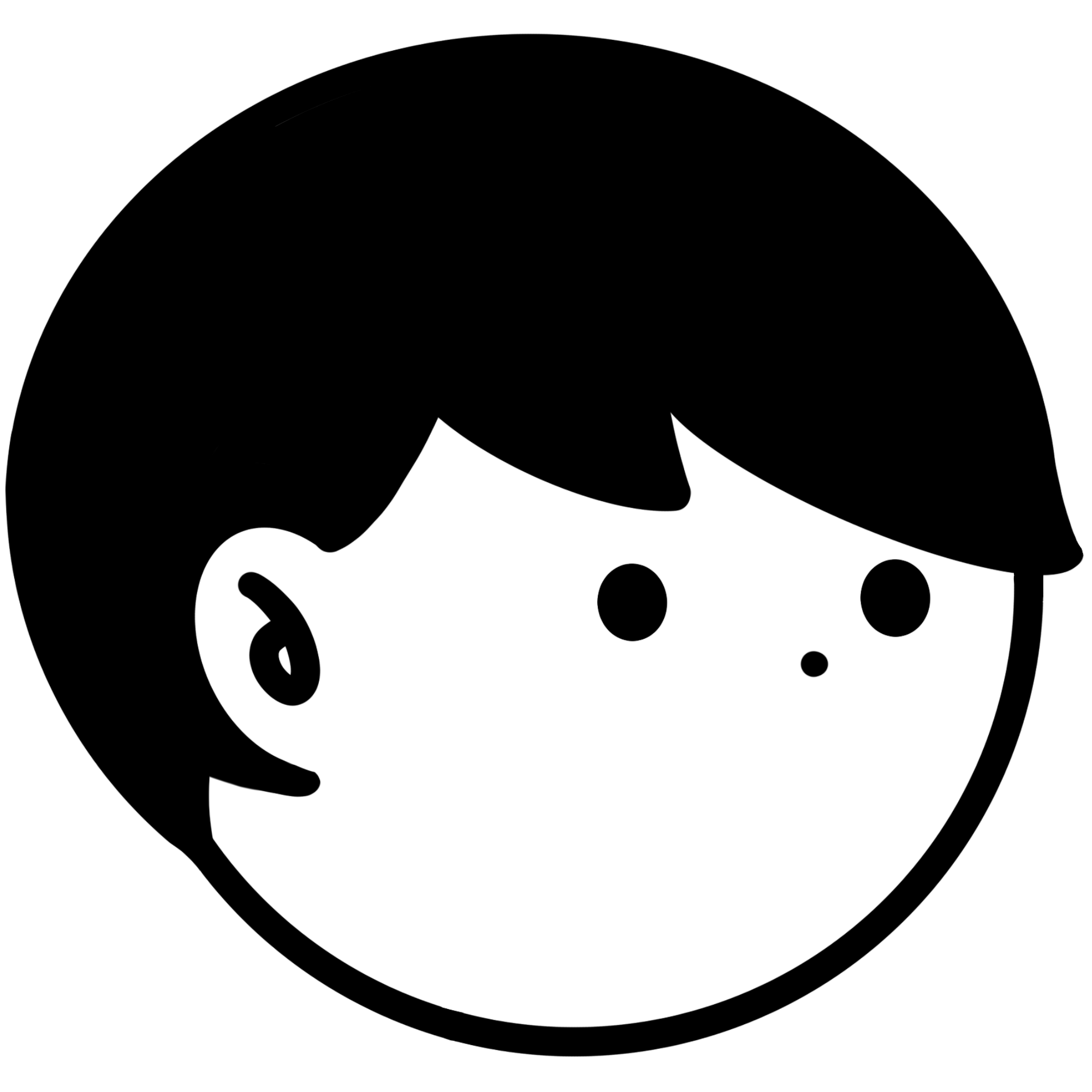
町長選挙、楽しみだね!
投開票日が10月19日(日)に迫ってきました、津和野町長選挙。
私たち町民にとっては、「津和野、これからどうなっていったらいいかな?」と町のことをいつもよりも深く考えることのできる良い機会ではないでしょうか?
候補者が考えていること、伝えたいこと、見ている景色、熱い想い。
短い選挙期間だからこそ、少しでも多くの町民の方々がそれらの情報に出来るだけ多く触れることができるように、公開質問状という形式で両候補者へ16個の質問を送付しました。
(今回、合計40個を超える質問が集まりました。質問をお送りいただいた皆様、ありがとうございました!)
以下で両候補者からいただいた回答を質問ごとに掲載いたします。
【9個のカテゴリ】や【16個の質問目次】の各項目をタップしていただくことで、気になる質問と回答へすぐ移動することもできます!
じっくりとご覧ください🙇
候補者の紹介
16個の質問目次

立候補した理由と、御自身の強みをどのように町政に活かせるか教えてください。
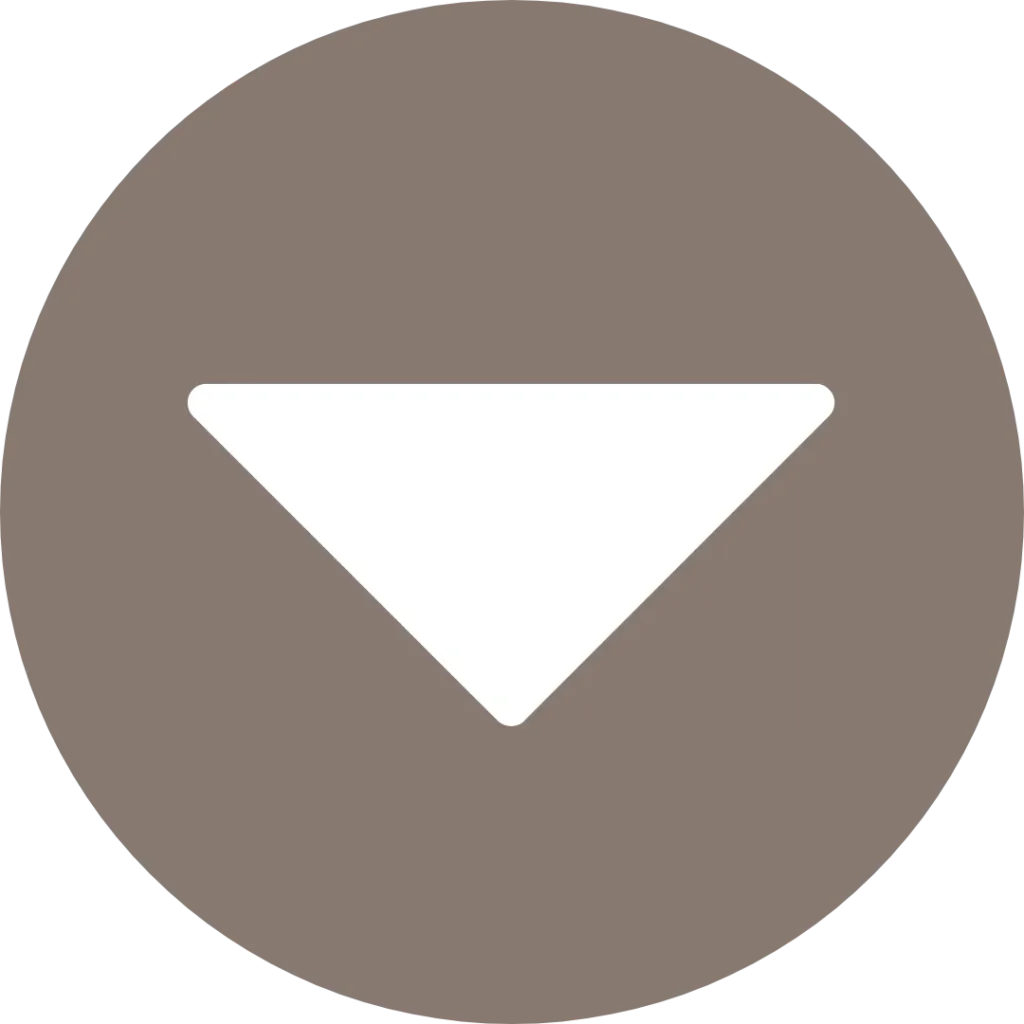

現状の『行政の状態』に点数をつけるとしたら何点ですか?
また、100点の場合にはその理由を、100点未満の場合にはその理由と具体的な改善点を教えてください。
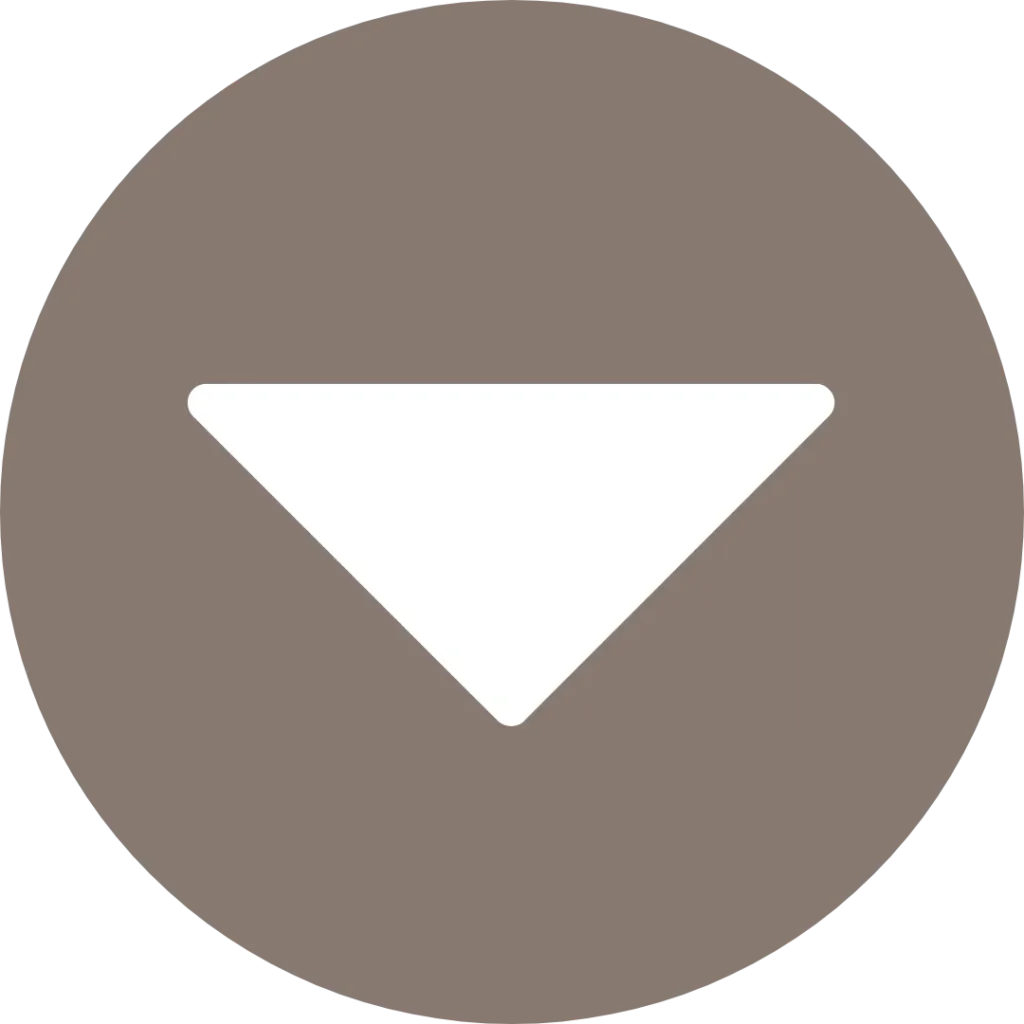

下記の2点についてお考えを教えてください。
①中長期的に町が目指す姿(どんな町※定性、人口やその構成や経済状態など※定量)と、それを達成するための戦略、それを叶えるための4年間で実施する手段(実施策)について
②どの指標で町政の成果を見るのか
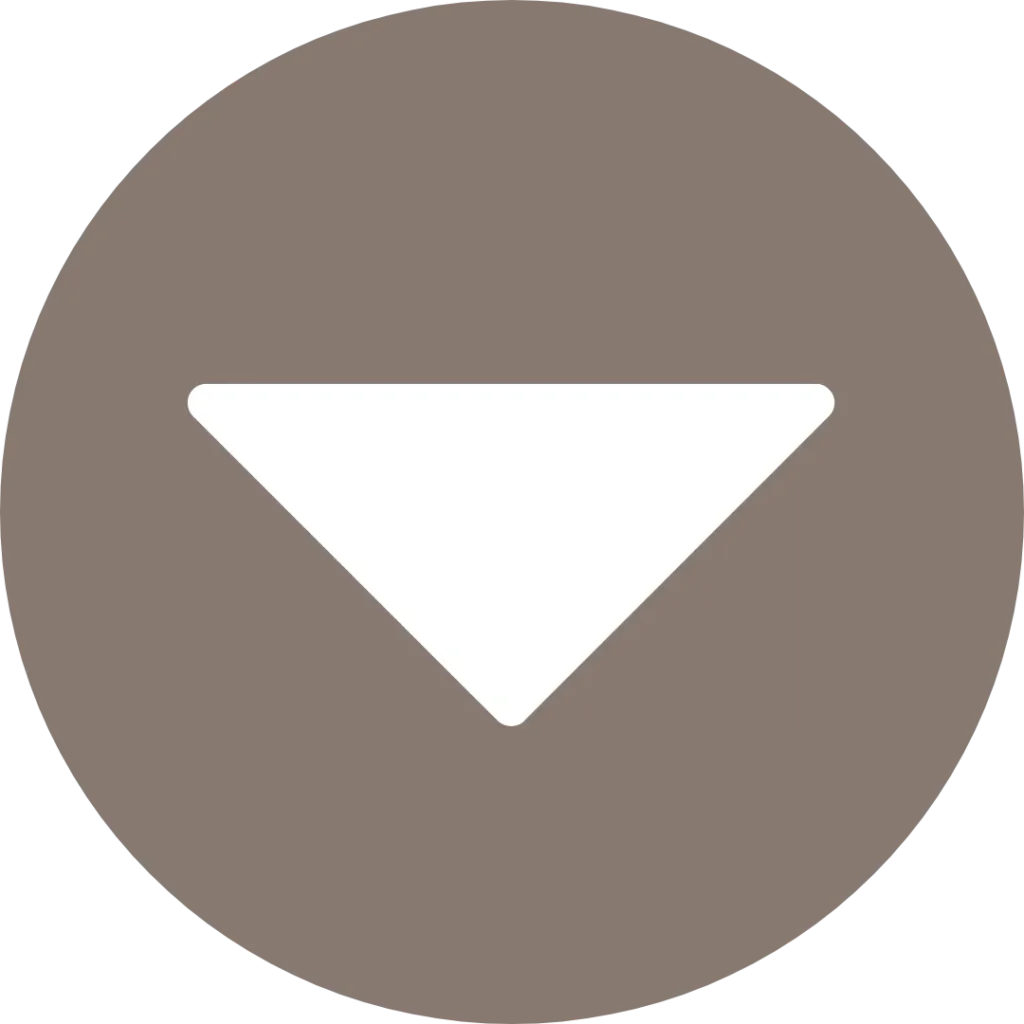

従来の津和野町の定住施策の課題をどのように認識され、今後の定住対策をどのように具体的に展開されるお考えでしょうか。
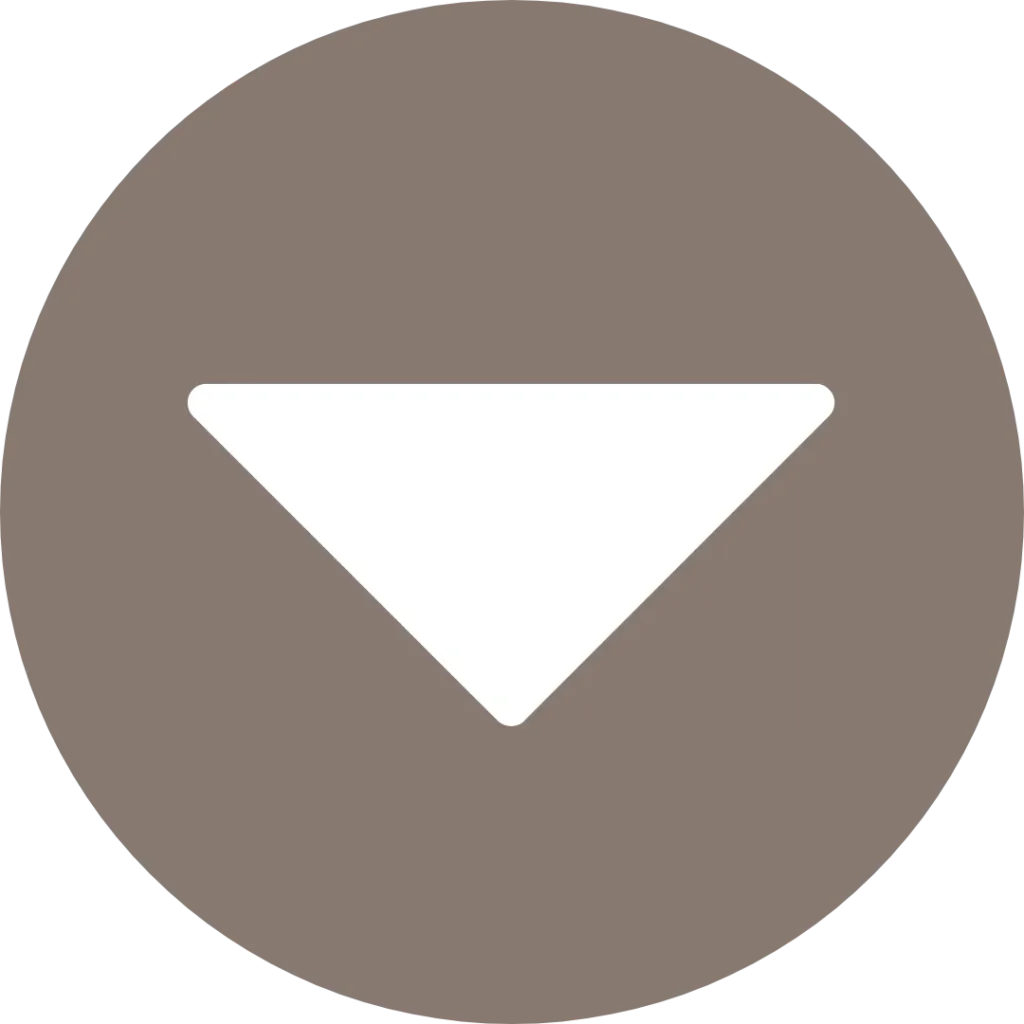

今後の津和野町東京事務所の存続について、どのようにお考えでしょうか。
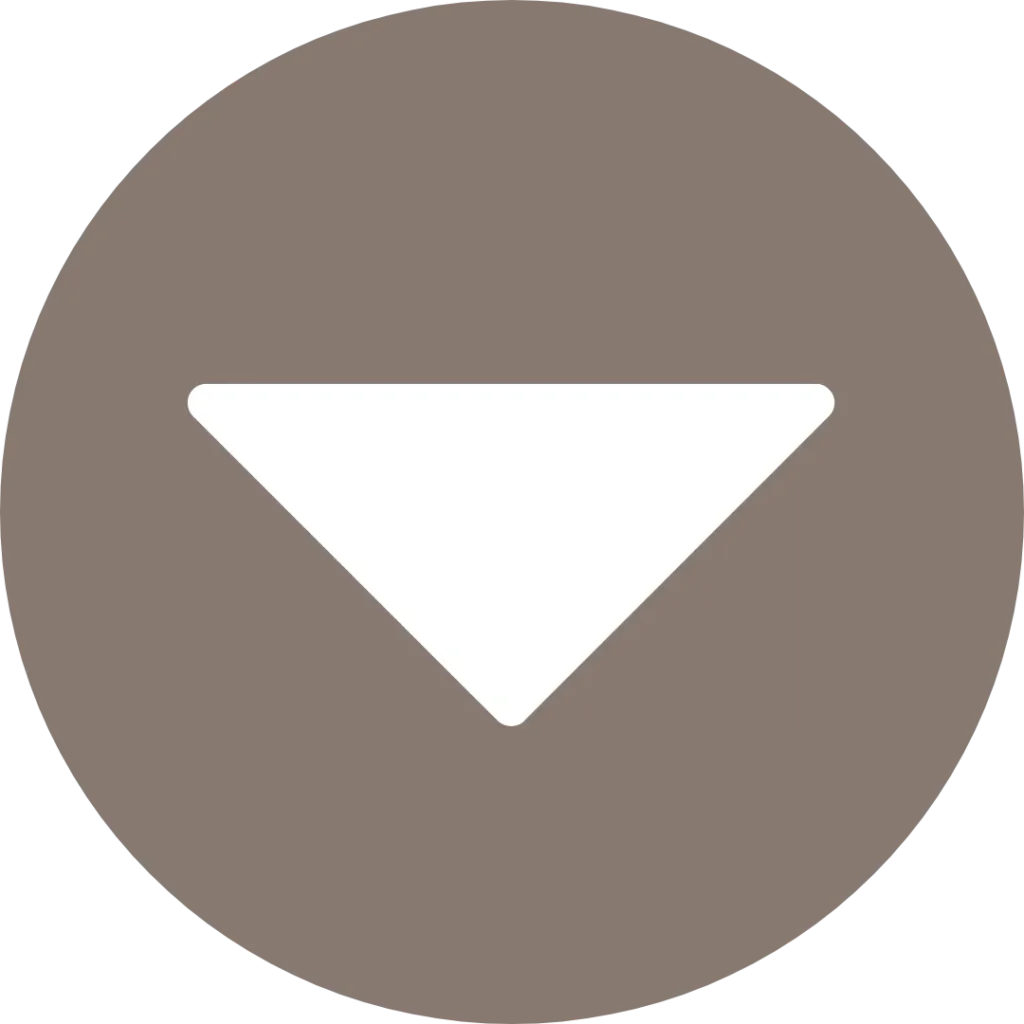

2030国スポを町全体で盛り上げるための戦略を教えてください。
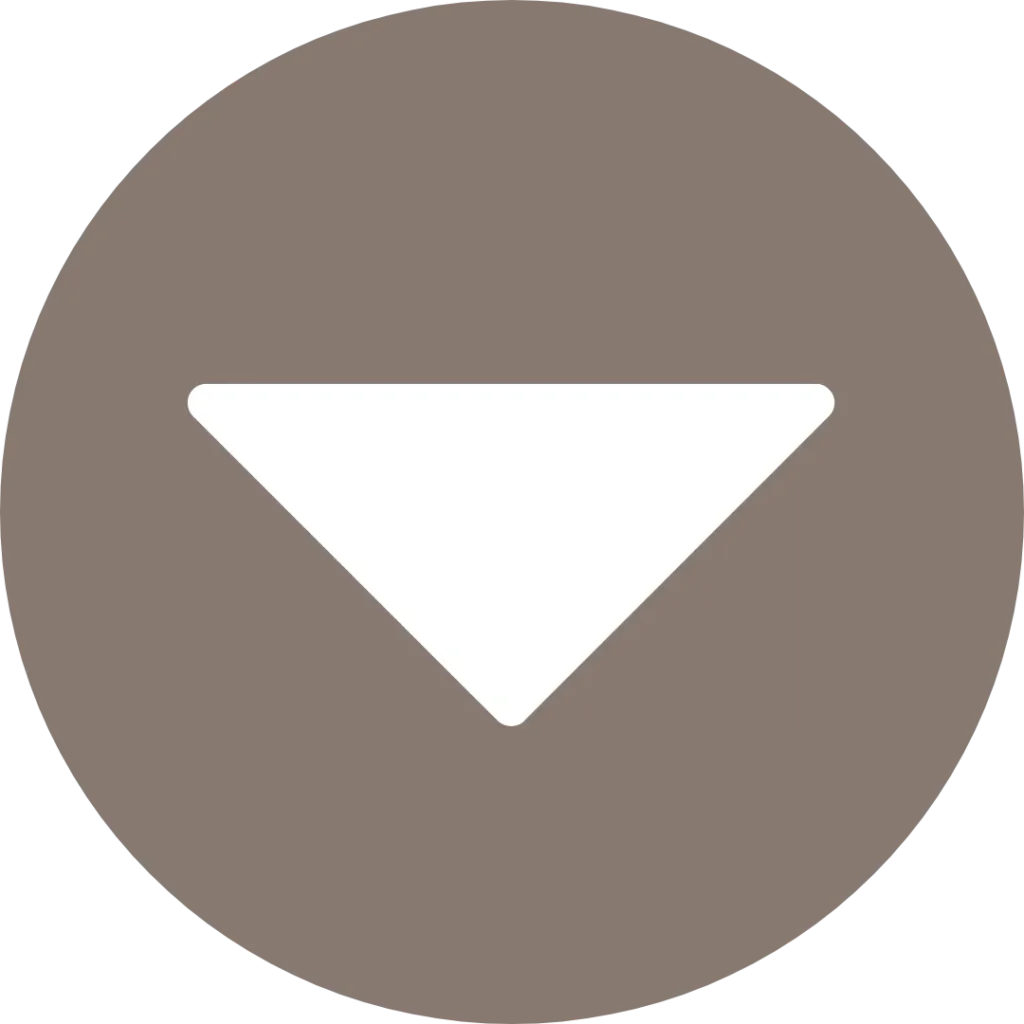

津和野町が進めていく町政において適当な職員を採用していく為の策は、どんな事があると考えますか?
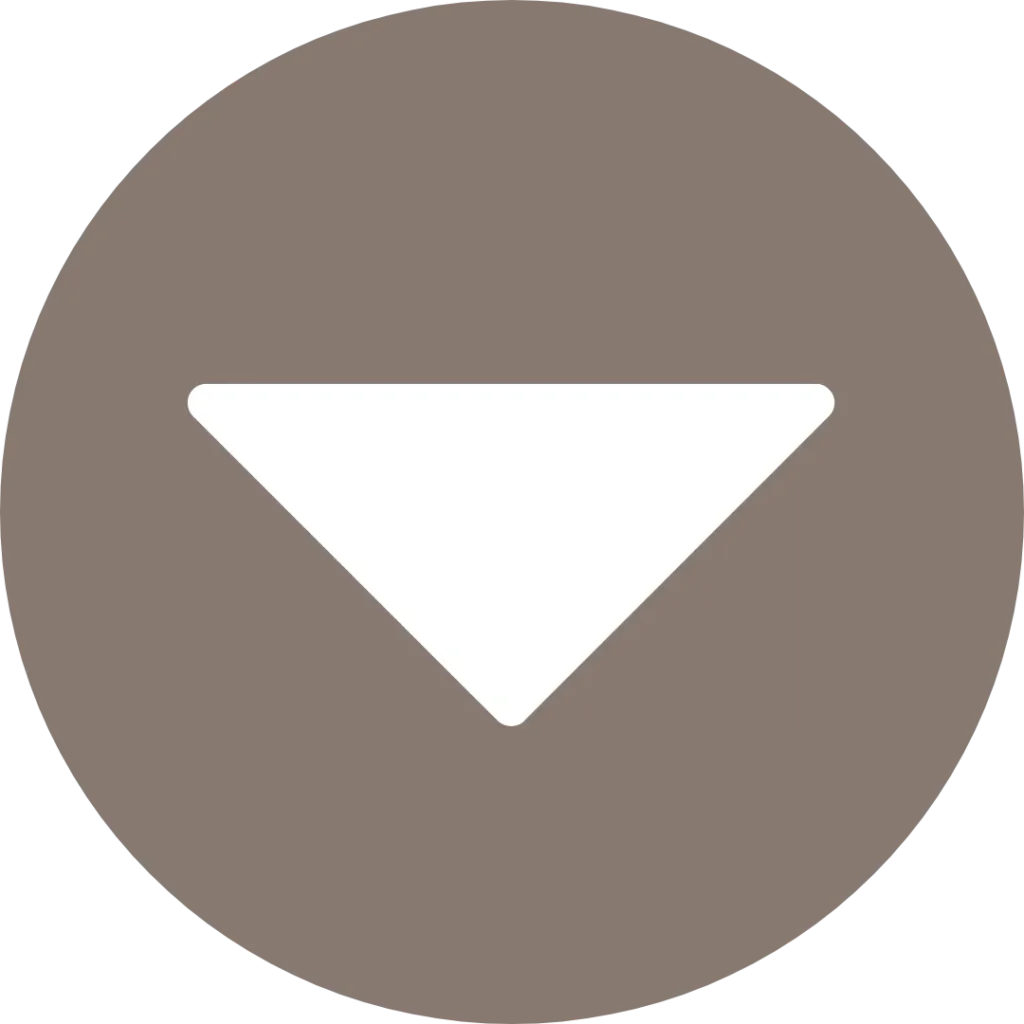

社会教育を通した町づくりをどう考えていますか?
そのための方向性の1つとして、公民館職員の雇用や待遇について改善していく方針があるのかお聞かせ願いたいです。
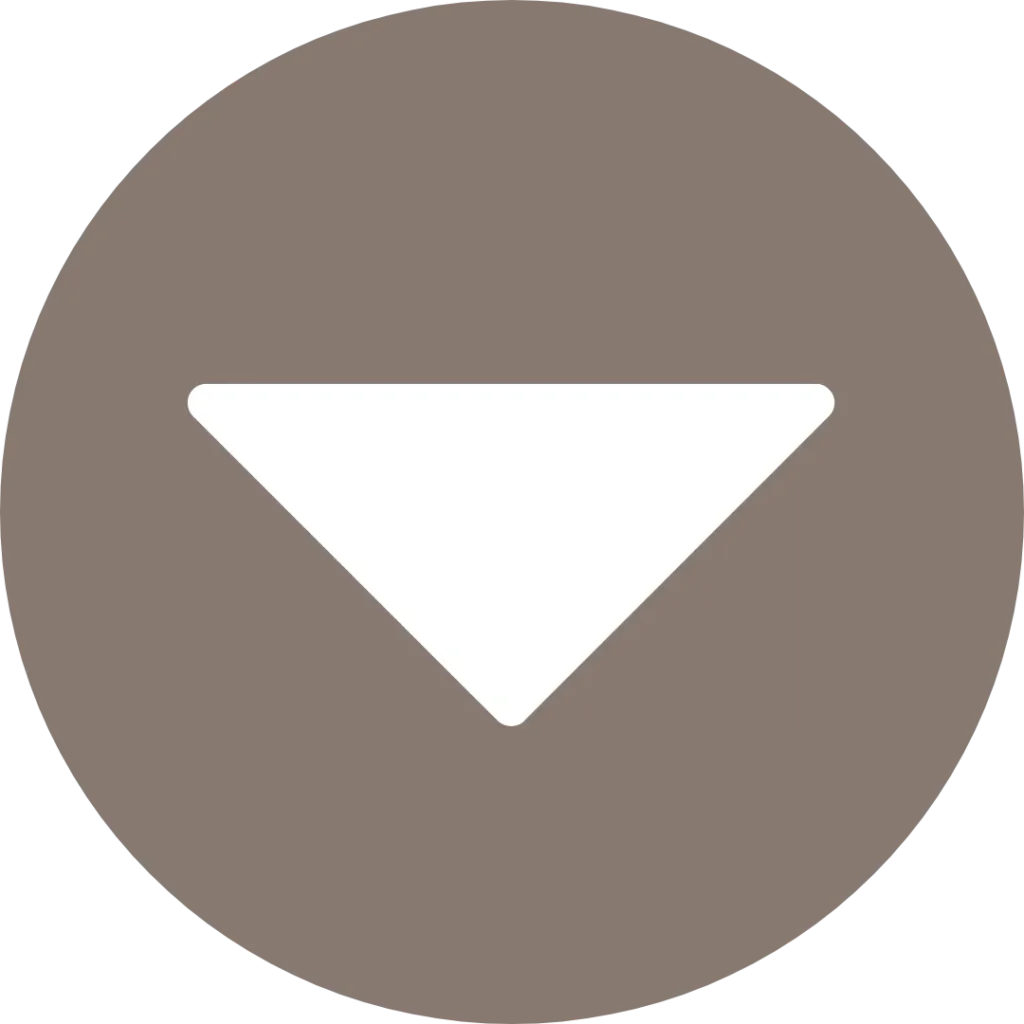

子育て世帯の定住や転入を促すために、任期の4年間で特に優先する施策を優先順位とともに具体的にお聞かせください。
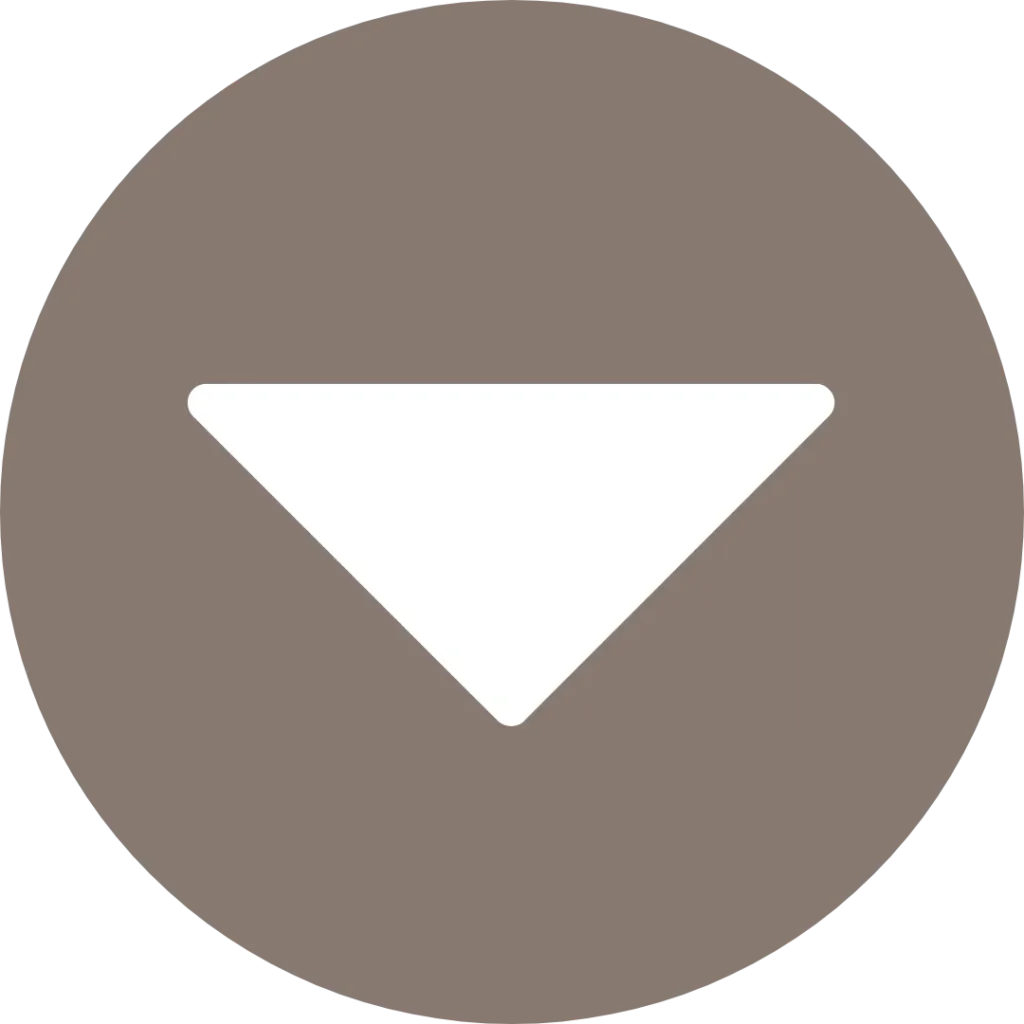

給食無償化を単なる『無料化』で終わらせず、『地域資源を活用した質の高い食育の機会』へと昇華させるため、どのような具体的な解決策を講じていくお考えですか。
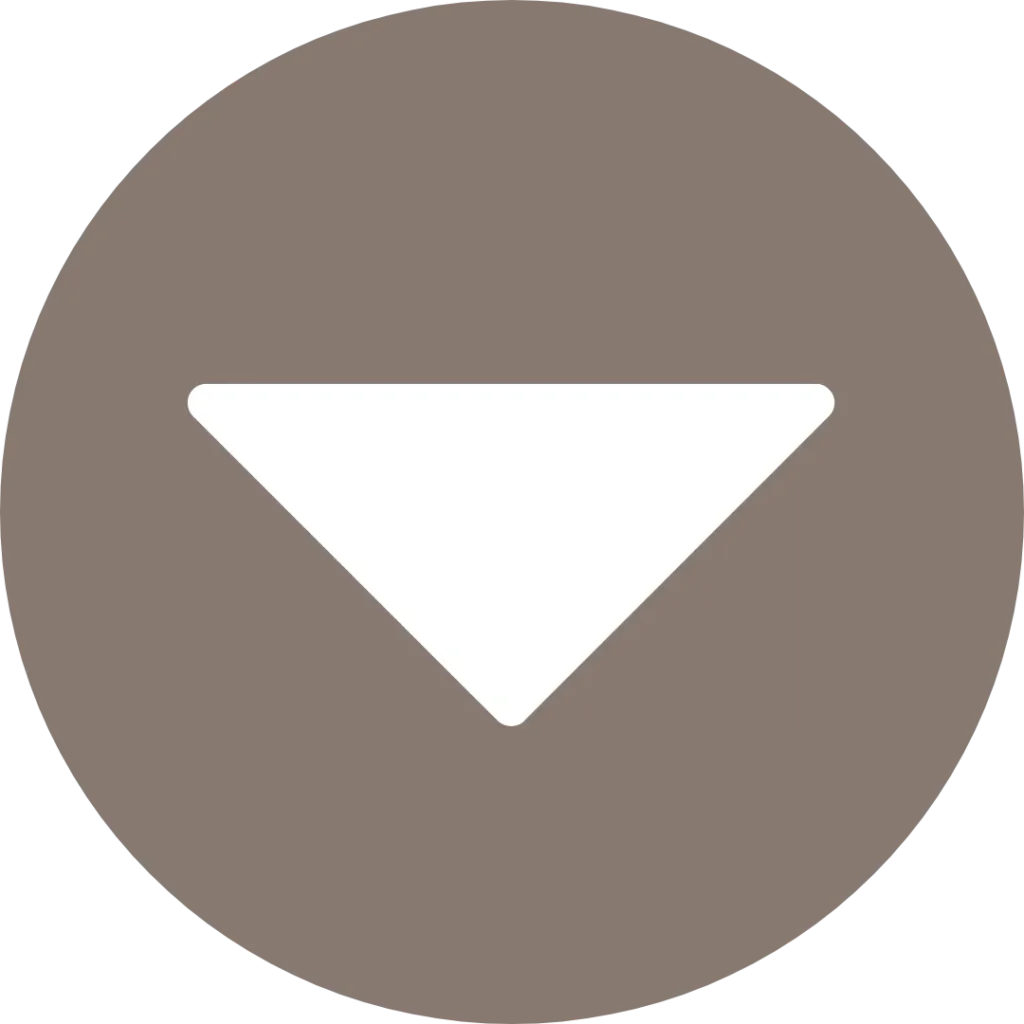

観光振興計画にとどまらず、町長として2030年のインバウンド戦略をどう描き、どのように実行していきますか?
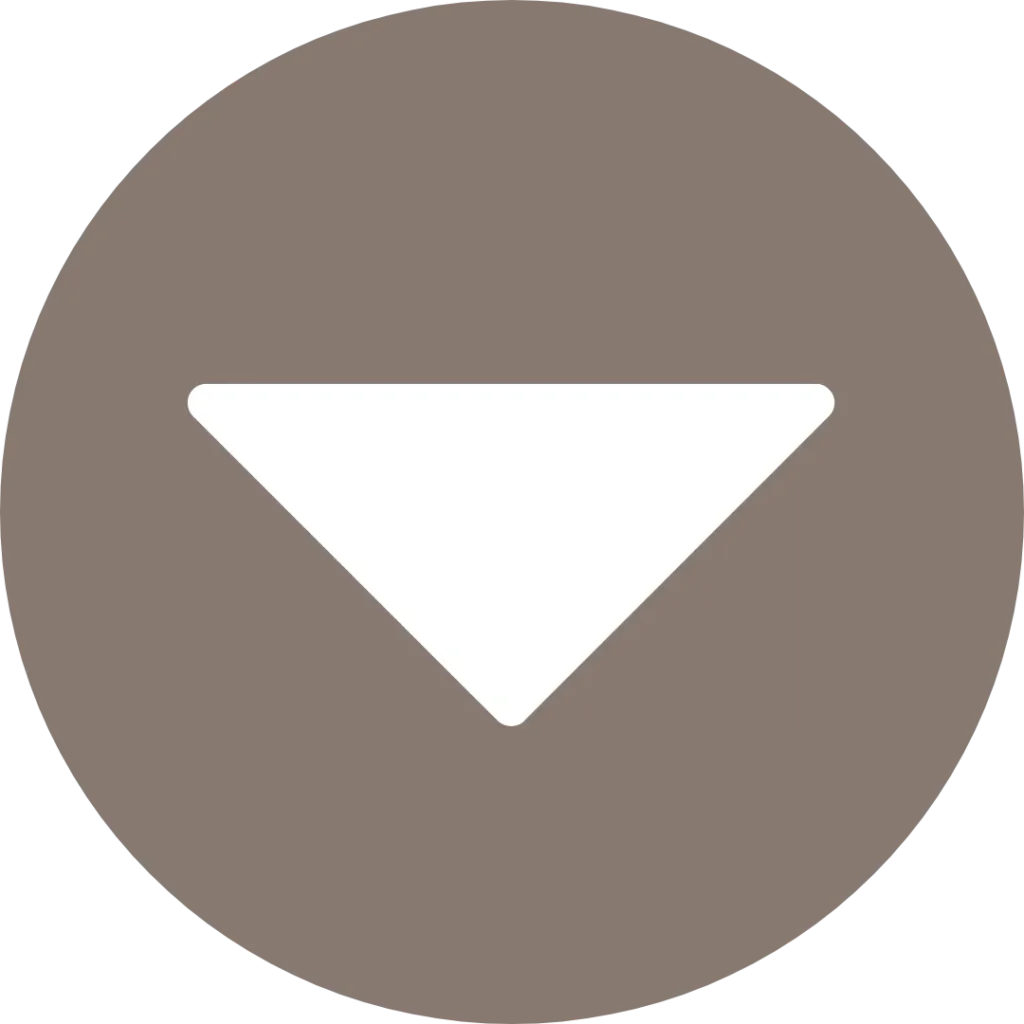

津和野町民センターの施設耐震改修に伴う、文化ホール増築の要望が2025年6月の一般質問でありましたが、賛成でしょうか?反対でしょうか?
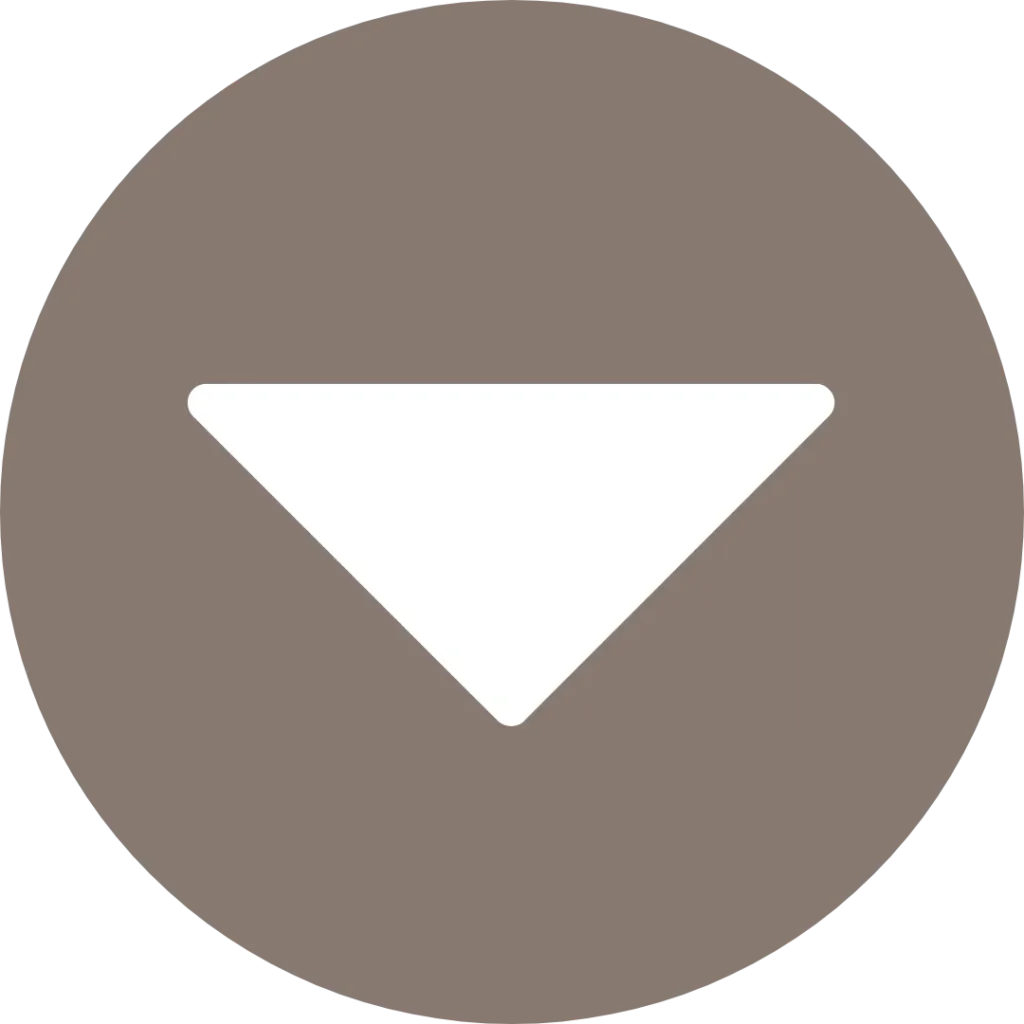

これからの高齢者の移動手段の施策とその施策の根拠を説明してください。また、その施策は何年後までに実現しますか?
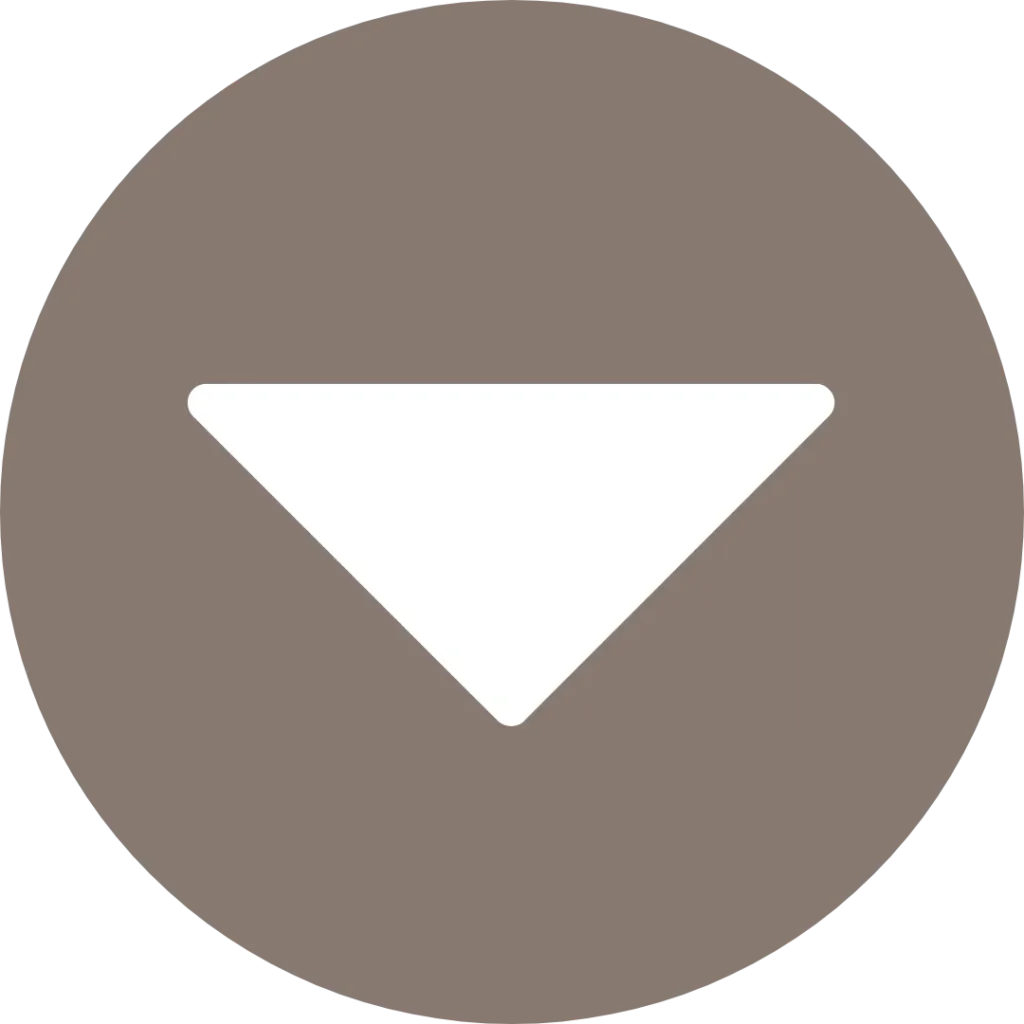

高津川の清流を守るため、「災害に強く、多様性のある水源の森」をどのように育て、野生動物との「住み分け」を促す森林整備をどのように進めていくお考えですか?
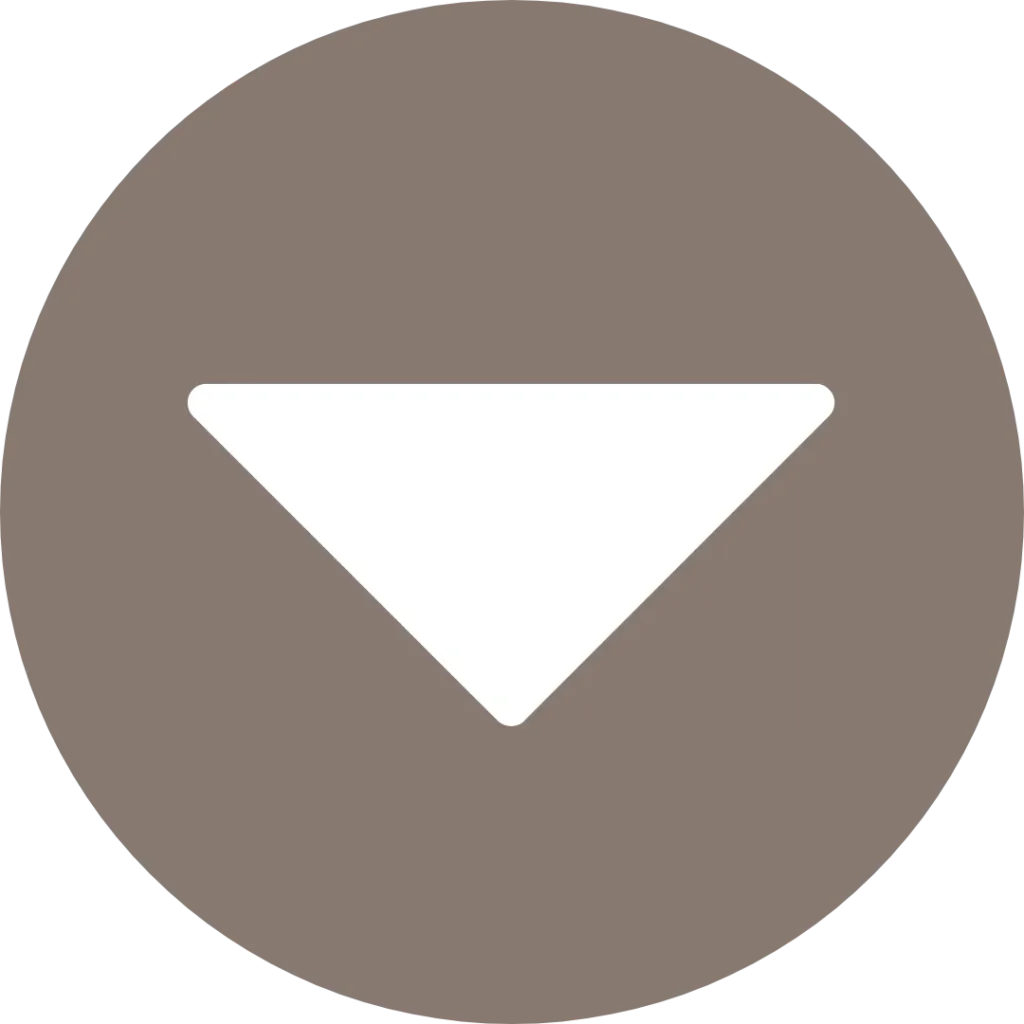

農業の担い手不足について、現状の農業体験事業を都会にPRするだけでは、解決に至らないのではないでしょうか?
その他にどんな対策を講じていくつもりでしょうか?
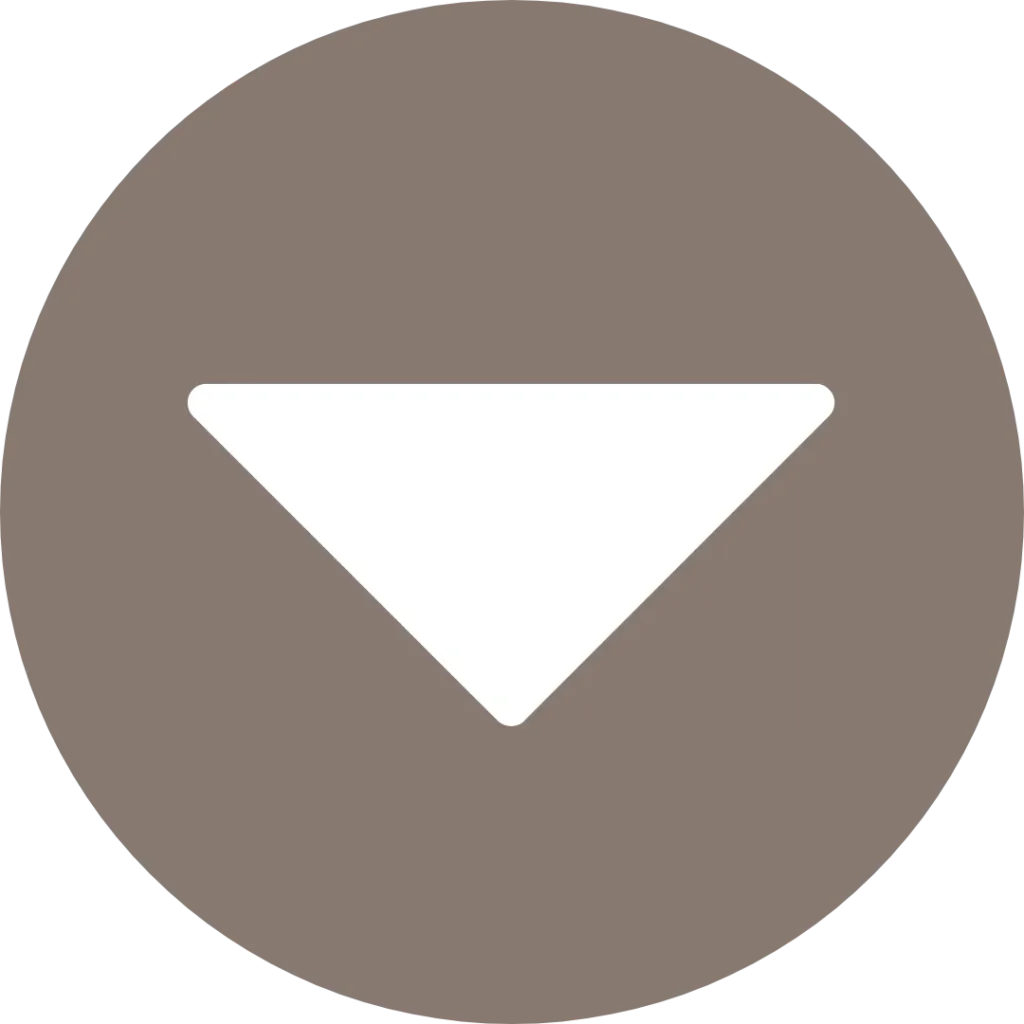

木質バイオマスガス化発電の今後の展開について考えを教えてください。
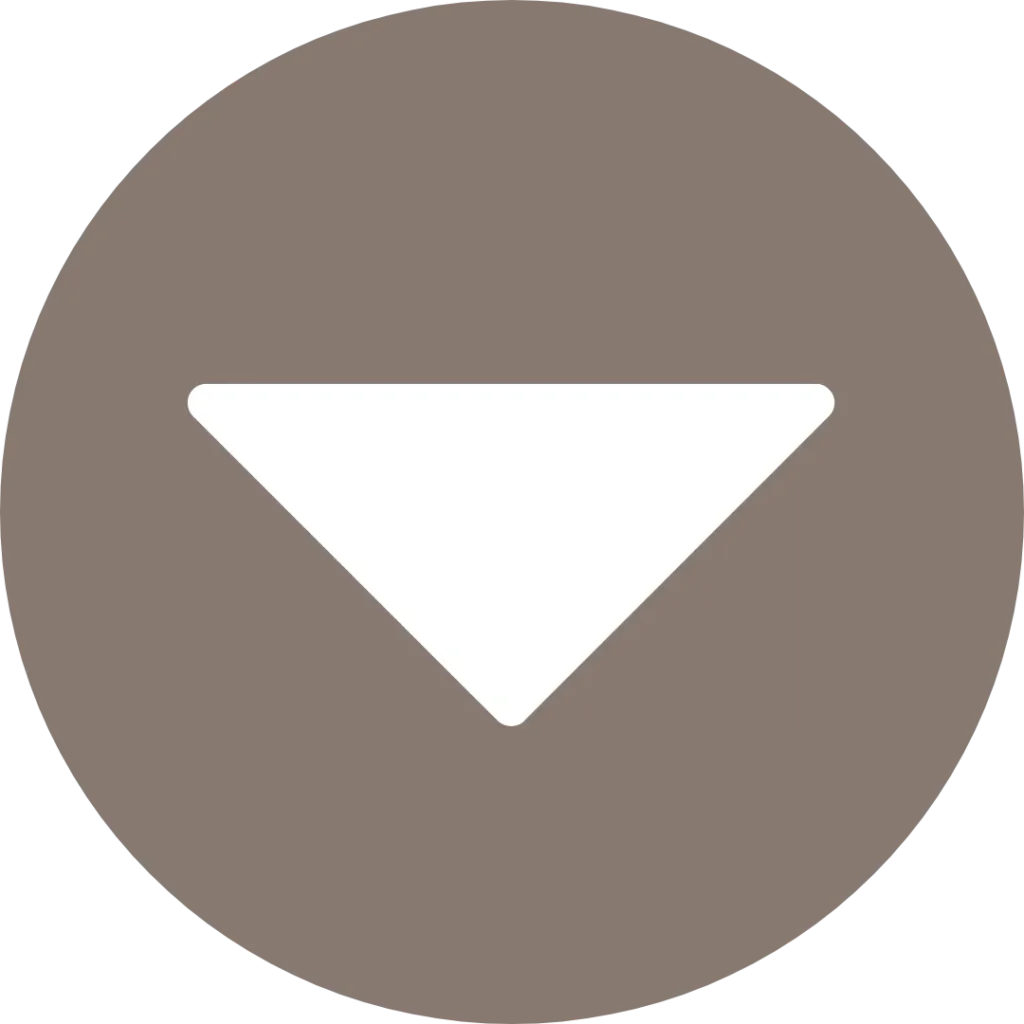
質問と回答

👀 候補者の考え
立候補した理由と、御自身の強みをどのように町政に活かせるか教えてください。
現職につきましては「5期目への立候補」という意気込みについても考えをお聞かせください。
あわせて、今期より力をいれて実施したい政策を1位から5位までお答えください。
候補者からの回答
 下森候補
下森候補 過疎高齢化の中で住民生活へ密接に関わる様々な問題が生じこれまでも解決を図ってきましたが、今後も課題の解決と合わせ特に物価高が進行する過渡期において、住民生活を守るための対策が重要課題として浮上し、それに向き合う責任を強く受けとめたことが大きな理由です。
強みとしては町政を進める上で多くの仲間がいることです。16年前の初陣の時から私の政策に賛同して下さった方、そして現在までにその輪は広がっております。もちろん批判も多くあることを自覚しており、その上で全ての町民が幸せになることを目的に町政運営に臨んでおりますが、まちづくりに仲間の存在は欠かせません。この度も出来るだけ具体的に公約を掲げ賛同して下さる方を増やす機会に出来ればと思っております。
合わせて本町の自主財源は年間総予算の1割程度であり、国等へまちづくりの財源を依存しております。予算の効率的かつ効果的な執行は常に意識しなければなりませんが、財源の確保は町政運営の生命線と考えております。これまで培ってきた人脈とネットワークは私の財産であり、財源の確保と制度の拡充などについて力を発揮したいと思います。5期目だからこその私の使命であると思っております。
重視する政策で順位はつけられませんが、〇本町ならではの教育の魅力化を進め、生きる力をもった人をつくることと、教育の町としての魅力を定住対策へつなげること、〇各種災害や異常気象に備え町民の生命と安心を守る防災機能の強化を進めること、〇高齢者や障がい者、子育て世帯などを対象とした福祉について、住民が笑顔で暮らせるよう充実させて行くこと、〇自然や文化財など本町には本物の価値をもつ財産が豊富であり、観光等の産業振興へ活かした取り組みを進めること、〇コロナから物価高へ移行する中で大きな影響を受けている住民生活や町内産業を守る対策を講じることです。



津和野には、想いをもって行動する人がたくさんいます。教育、子育て、地域づくり、農業、福祉など、あらゆる現場で懸命に動く方々がいます。けれど、その力が一つにまとまらず、未来の方向が見えにくくなっているのが今の津和野の現状です。
私は、今こそ「津和野がどんな未来を目指すのか」をみんなで描き、世代や立場をこえて協力できる町にしたいと思い、町長選に立候補しました。 町民一人ひとりが希望を持ち、「津和野に生まれてよかった」と感じられる町をつくる——その旗を掲げるためです。
これまで私は、ひとづくり・まちづくりの現場で挑戦を続けてきました。強みは3つあります。
一つ目は、対話でつながる力。立場や世代をこえて語り合い、互いに安心して意見を出し合える関係をつくり、共通のビジョンを見いだしてきました。
二つ目は、人の挑戦を後押しする力。 子どもからシニアまで多様な世代の想いに向き合い、挑戦を支え、その実現を仕組みとして形にしてきました。
三つ目は、価値ある仕組みを創る力。 一人の困りごとを社会の課題として捉え、共感を広げながら未来につながる解決策を実装してきました。
これからの津和野町政では、この3つの強みを生かして、次の5つの政策を柱に据えます。
①津和野の魅力のブランド化
②津和野の魅力の戦略的発信
③町民の挑戦を後押しする人材育成
④対話的な会議の推進
⑤官民連携の仕組みづくり
安心して暮らし続けられる津和野を実現するために、この5つの政策を軸に全分野で改革を進めます。この内容は、私のnoteに掲載のチラシでも分かりやすく紹介していますのでぜひご覧ください。


📕 まちの戦略
現状の『行政の状態』に点数をつけるとしたら何点ですか?また、100点の場合にはその理由を、100点未満の場合にはその理由と具体的な改善点を教えてください。
例として、『行政の状態』を測るための判断項目を10個ほど挙げます。下記の判断項目に沿って行政の状態を評価していただいても結構ですし、使用せずに回答をしていただいても問題ありません。
補足
質問の意図としては、今の津和野町の住民意識や行政職員の方々の仕事の状態を見るに、「行政職員さんに頼りすぎ=住民の自律性が少ない」のではないかと考えています。
行政には行政にしか出来ない仕事が山ほどあるはずですが、余計な負担が行政にのしかかってしまっては「やりたいしやるべきだと思っているが、忙しくてそれどころではない」という状態になってしまい、行政の職員の方々が疲弊していってしまうのではと危惧しています。
そのため、行政の長たる町長、その候補者が今の行政のあり方をどう評価するのかを知りたいと思い、質問をしています。
『行政のあり方』を測る判断項目(例)
職務分担の妥当性
└ 業務の割り振りが過不足なく行われているか
各課の連携・情報共有
└ 部署間での横断的な協力体制・スピード感
職員の業務意識・モチベーション
└ 津和野町職員としての責任感・やりがい・住民目線
住民への説明責任・情報公開
└ 分かりやすさ、タイムリーさ、双方向性の有無
政策立案力・実行力
└ 課題を把握し、解決に向けた企画を実行する力
地域課題への即応性・柔軟性
└ 災害対応や人口減少対策などへの迅速な動き
財政運営の健全性
└ 無駄のない予算配分と持続可能な投資判断
市民参画・協働の姿勢
└ 住民や民間事業者との協働をどの程度重視しているか
地域資源活用・ブランディング力
└ 津和野らしさを引き出し、内外に魅力を発信できているか
長期ビジョンと実行の一貫性
└ まちづくりの方針が一貫しており、ブレずに進めているか
候補者からの回答



現職にとりましては回答に困るご質問を頂いたというのが正直な気持ちです。
点数をということですが、合格点であれ落第点であれ、組織の長が十分な内部協議と職員との共通認識に立つことなく、自らの思いのみで点数評価を公開してしまうことは、職員との信頼関係を損なうことにもつながりかねず、組織運営上において問題が生じることへの配慮をしなければならないと認識しております。
もちろん日頃から人事評価や行政評価制度を導入するとともに、組織全体や個々の職員の状況についても他の管理職と把握し評価する努力をしておりますが、現時点で点数評価として公開するまでの水準には至っていないと、反省と合わせ認識しております。
これまでの経験から公平公正な評価作業の重要性と難しさを感じておりますが、この度のご質問で「行政のあり方を測る判断項目(例)」をお示し頂きました。今後それに基づいた評価を行うことも有効と受けとめたところでもあり、参考にさせて頂くため、より具体的な評価指標など、町メールアドレスなどを通じ教えて頂きましたら幸いに存じます。
津和野町役場全体として内部評価の共通認識に立つことが出来たあかつきには、住民に公開し外部評価を頂くことを通して、住民の期待に応えられる組織へと近づけて行けるのではないかとご質問を受けて考えました。
そしてそのよう仕組みをつくり実践する過程を経ることで、「補足」で述べられている行政の負担軽減にもつながるような住民協働のまちづくりが実現できるとも期待しております。
ご質問に対する的確な回答とならないことを改めてお詫びいたします。



津和野町の行政を10項目で自己評価したところ、合計でおおよそ50点となりました。ただしこの点数は、行政職員の能力を評価したものではありません。職員の皆さんは真面目で優秀な方が多く、町への思いも強いと感じています。低い点数となった理由は、行政の仕組みや方向性、そしてトップのビジョンとマネジメントに課題があるためです。
特に課題と感じているのは、
①職務分担の妥当性
②財政運営の健全性
③市民参画と協働の姿勢
④地域資源の活用・ブランディング力
⑤長期ビジョンと実行の一貫性、の5つです。
現状では「維持すること」が目的化している業務が多く、本来の目的と手段がずれてしまった事業や、成果に結びつかない取り組みも見られます。 そのため新しい挑戦に取り組む余力が不足しています。また、職員に余裕がないことで、民間や住民の活力を十分に引き出す関わりができていない現状もあるのではないかと感じています。
私は「現状維持は衰退、挑戦と進化こそが発展」と考えます。トップが明確なビジョンを示し、変化を恐れず、形骸化した事業を整理していくことで、職員が挑戦できる環境を整えます。
行政は「お金にならないことを仕事にできる」唯一の存在です。 町民が挑戦し、稼ぐことで税収が増え、教育や産業に再投資できる循環を生み出す。民間が挑戦し、行政が後押しする—そんな信頼関係を築き、少数精鋭の津和野町行政を実現したいと考えています。


📕 まちの戦略
下記の2点についてお考えを教えてください。
①中長期的に町が目指す姿(どんな町※定性、人口やその構成や経済状態など※定量)と、それを達成するための戦略、それを叶えるための4年間で実施する手段(実施策)について
②どの指標で町政の成果を見るかについて
補足
4年で成果が出る!
どの成果をゴールとするかを決めて町民6300人みんなでその達成へ向けて地道に一歩ずつ頑張りたいですね。
候補者からの回答



津和野町では総合振興計画を最上位計画とし、地域福祉計画や観光振興計画、教育ビジョンなど、分野ごとに計画を策定し、それらに基づいた施策と事業を展開しております。
定住や人口減少対策分野については、まち・ひと・しごと創生津和野町総合戦略を定めており、その中で評価をするための指数(KPI)を項目ごとに設定し、達成度合いや効果の検証などを毎年実施しております。
時代の移り変わりとともに社会環境も変化いたしますので、これらの計画については多くが10年というスパンで策定し、そのうちの前期5年を目途に見直しを図っておりますが、特に総合振興計画と総合戦略については、津和野町総合振興計画等審議会を設置し、民間の代表の方々から評価と検証を毎年頂いて町議会にも報告しております。
尚、総合振興計画は平成20年に策定され、見直しを行いながら現在は第2次の後期計画段階にあり(令和4年度から8年度)、総合戦略は平成27年度に策定し第2期(令和8年度まで)を迎えております。
全ての計画が住民の皆さまとともに策定したものであり、町長として公約として示すものも、基本的にはそれらの計画を尊重したものであるべきと考えております。
ひとつひとつの計画はボリュームもあり、全ての皆さまに共有して頂くのは現実的に不可能かと思いますが、それでもご指摘のようにより多くの方々の理解を深め住民の皆さまが達成に向け協働の活動を展開して頂けることは本町の発展にとって重要です。
今後は計画づくりや評価・検証作業において公募の枠を増やすなど、住民参画の機会を拡充し、より一層の住民理解を深め協働の輪を広げる努力をしてまいりたいと思います。



◎向こう10年のビジョン
私が目指すのは、「町民が誇れる・外から選ばれる町」です。人口規模が小さいからこそ、行政も住民も顔が見える距離で支え合い、誰もが“一人の町民として”意見を出し、行動できる。 一人ひとりが“自分ごと”として町の未来を考え、地域の誇りと魅力を高め続け、次の世代へ確実につなぎ、小さくても力強く、挑戦し続ける町を作ります。
◎定量・成果指標
①社会減の抑制(年間50人の転入を目標)
②働き手世代(15〜64歳)の定着・流出抑制による税収の確保
③町民の暮らし満足度
◎その実現に向けた戦略・手段
①対話的な会議の推進と官民連携の仕組みづくり
②一人ひとりの力を伸ばす人材育成
③津和野の魅力のブランド化と戦略的発信
◎この4年間では、まずその土台を築くために、
・地域・学校・行政の協働体制の整備
・プレーパークや地域食堂など共助型コミュニティづくり
・高校生や若者が地域で挑戦できる仕組みづくり
・中山間地域の移動・生活支援モデル構築
を優先的に進めます。
◎成果の指標としては、人口の増減だけでなく、
町民の「満足度」「関わり度」「誇り度」を数値化し、
町民6,300人が「この町にいてよかった」「自分も一歩、動いてみよう」と感じられる状態をゴールとします。町の未来は、誰かがつくるものではなく、みんなで育てていくもの。その一歩を、この4年間で確実に進めていきます。


📕 まちの戦略
人口減少が進む中で、定住対策は町にとって最重要課題の一つであると考えます。
これまでの施策は外部からの移住者を募ることが中心であったように見受けられますが、移住者には住居の確保や、津和野という町に馴染めるかどうかといった課題があります。そのため、必ずしも定着に結びつかないケースもあります。
一方で、地域に縁があり生活基盤を築きやすい「Uターン者の促進」は、より効果的な定住策になると考えます。
従来の津和野町の定住施策の課題をどのように認識され、今後の定住対策をどのように具体的に展開されるお考えでしょうか。
候補者からの回答



UターンとIターン共に本町の定住対策においては重要であり、これまで高校生までの医療費の無償化、保育料の無償化、保育園等へのおむつやお米の無償配布など、子育て支援策を実施してまいりました。
また昨年よりは、つわのスマイル応援事業というような町内在住者を対象としたリフォーム支援も始めております。
ご指摘にようにUターンの促進は、もともと津和野町に縁のあった方々が対象となるため、定住実現に向けて近道となる可能性を認めております。
一昔前は本町に働く場がないためUターンが難しい要因が指摘されておりましたが、近年は町内のあらゆる産業が人手不足となっており、雇用の機会は確保されている状況にあります。
もちろん、都市部との賃金格差があることは認めざるを得ませんが、上記に示したような子育て負担の軽減策や低廉な住居環境等が格差を埋める手立てになることを期待してもおります。
あとは、町内の各世帯が子どもさんやお孫さんにUターンを促す気持ちをもち、訴えて頂くことが大切であり、それを促進する取り組みを今後は展開したいと考えております。
子どもさんやお孫さんと一緒に、または近くで暮らすことのできる生活は、高齢者にとっても生きがいのもてる福祉の増進に通じるとも思います。
そして、現在のまちづくりの柱と考えている教育の町・津和野町の推進による教育の魅力化を通して、郷土愛を育み、本町の将来を担うひとづくりを行いながら、Uターンを促進してまいりたいと思います。
教育を重んじてきた歴史をもつ本町が目指す方向として、信念をもって地道に取り組みを続けることで、時間は要しても必ず花が開くと信じております。



移住者は、IターンであれUターンであれ、 一度住み始めたら、もう立派な「町民」です。私は、町が「来てくれる人は町の宝だ」という姿勢を持ち、 移住者・定住者の区別なく、つながりを大切にできる町でありたいと考えます。
これまでの施策は「呼ぶこと」が中心で、移住後の暮らしや関係づくりの支援が十分ではありませんでした。
しかし、本当に大切なのは「来てもらうこと」ではなく、「この町に来てよかった」と思える関係を育てることです。そのため、移住後の満足度を高める交流や伴走の仕組みを整えます。移住者が地域の人と出会い、移住者自身の強みを活かして活躍できるような応援体制づくりを進め、共にまちをつくる仲間として迎えます。
Uターン促進に関しても、都会で働く津和野出身者のネッワークをつくり、オンラインで町づくりに関わってもらい、「いつか帰りたい」と思ってもらえる仕組みを作ります。
さらに、将来のUターンにつなげるにはふるさと教育が不可欠です。子どもたちが地域の人や自然、文化を体験し、「自分の町を誇りに思う」気持ちを育てることが、 いつか「津和野に帰りたい」と思う原点になります。
町民一人ひとりが自分の町の魅力を語り、官民が協働してそれを発信していく。 その循環が、“外から選ばれ、内から愛される町”を実現すると信じています。


📕 まちの戦略
津和野町東京事務所が開設から10周年を迎えたと伺いました。町のホームページ等で発信されている活動内容を見る限り、現在の活動であれば、わざわざ津和野から職員を常駐させる必要性は薄いのではないかと感じます。
むしろ、津和野出身の在京者を採用して活動を担ってもらい、必要に応じて町の職員が出張する方が、現在の町の財政状況を踏まえると経費的にも合理的ではないでしょうか。
今後の津和野町東京事務所の存続について、どのようにお考えでしょうか。
もし存続させる方針であれば、職員を常駐させることの必要性をどのように位置づけておられるのか、お聞かせください。
候補者からの回答



津和野町東京事務所は様々な業務を担っております。定住対策では、年間を通して東京で数多く開催されている定住フェアにおいて、ブースでの来場者への営業と合わせ、フェア終了後も本町に関心をもって頂いた方々のフォローアップをする拠点として機能しております。
また、津和野高校の入学者数も魅力化と同時に首都圏を中心に増加しており、募集や相談などの窓口業務として高校存続の重要な一翼を担っております。
企業誘致関係では、既に本町へ進出頂いたIT系企業との交流による関係性の強化と合わせ、更なる誘致対象先の掘り起こしと営業を行っております。特に本年から始まった津和野高校の普通科改革を通して、今後更なるIT系企業の誘致が促進できる期待とともに、高校の卒業生にやがてU・Iターンをして頂くことを目的とした「還流」事業にも着手したところであり、東京事務所の役割は一層重要性を増すと思っております。
交流協定を結ぶ文京区との関係では、町内産のお米の生産と販売促進のための事業をはじめ産業や文化、教育、防災など多方面にわたる事業を共同で実施しております。
また本年は東京都の企業より高額な企業版ふるさと納税をして頂いておりますが、来年度以降の継続的な寄付や新たな対象先による高額納税の可能性が生まれており、東京事務所が存在することで円滑な交渉につながっております。
その他、萩・石見空港利用促進や観光振興など紙面の関係上省略いたしますが、こうした成果は責任ある正職員を配置していることにより生まれていると認めております。
これらの取り組みが住民の理解を十分に得られていないことは反省点であり、町議会に対して毎年実施している報告会のあり方をはじめ、対応を検討してまいりたいと思います。



東京事務所の存在意義は、単なる情報発信拠点ではなく、町と首都圏をつなぐ「人と情報のハブ」として機能することにあります。特に、国の方針や省庁の動きをいち早くキャッチし、町政に活かす“出城”の役割は、これからの津和野にとってますます重要になります。
そのうえで、事務所のあり方は、町職員の常駐の有無ではなく「誰を、どんな目的で置くか」が鍵です。文京区や関係機関との連携を深めるためには、現地に人がいることが欠かせません。ただし、必ずしも町職員である必要はなく、むしろ霞が関や都庁とつながり情報を掴む力、そして人材採用やPRに長けた専門人材を配置することで、東京事務所の価値を何倍にも高めることができると考えます。
町職員は、現地チームと密に連携しながら必要に応じて出張・伴走する形をとり、 事業の方向性を共有しつつ、戦略的に事務所を運営していきます。たとえ経費が一定かかったとしても、それに見合う成果を出せる人材とチームを組むことが、東京に事務所を置く意味を最大化することにつながります。
東京事務所は、Uターン・Iターン希望者や企業、学生、研究者など、 津和野に関心を持つ多様な人々をつなぐ拠点です。「津和野ファン」を広げる発信拠点として、成果を見える化し、町全体の利益と未来につなげていく体制へとアップデートしていきます。


📕 まちの戦略
2030国スポを町全体で盛り上げるための戦略を教えてください。
補足
現状、町民への周知がなく、盛り上がってない気がします。また町民に何ができるかもわからないです。
候補者からの回答



島根かみあり国スポ全スポ2030は、島根県内の自治体の全てが競技会場として運営の責任を負っており、津和野町は前回のくにびき国体の時に山岳競技を実施したご縁等によりスポーツクライミング競技に名乗りを上げ決定されております。
現在、大会成功に向け本番及び練習用の施設整備、競技力向上に向けた指導者の育成と確保、審判員をはじめスタッフの育成など、ハード・ソフト両面からの準備を始めており、住民あげての気運の醸成も大切な要素と認めております。
これまでは、まず子どもさんをはじめ住民の方々に当競技へ親しんで頂きたいとの思いから練習用のボルダーウォールを旧木部中学校体育館、津和野中学校、日原カントリーパーク内体育館に整備してまいりました。
また町内愛好者により津和野町スポーツクライミング連盟を創設頂くとともに、島根県及び島根県山岳連盟と競技の定着に向けた協定を結ぶなどし、連携しての普及活動を始めたところでもあります。
今後は、日原カントリーパーク内体育館にリードウォールを整備し、既存のボルダーウォールの活用と合わせローカル大会を実施する計画であり、実際に多くの町民の皆さまに迫力ある競技の模様をご覧頂くことで、理解を深めながら気運の醸成へとつなげてまいります。
尚、施設整備費用の心配をされる方もいらっしゃるかと思いますが、島根県の支援を頂き、町財政への負担を出来るだけ軽減することに努めながら準備を進めております。
2030年の大会終了後も当競技が本町の教育や地域振興に活かされて行く財産となることを心がけながら、大会に向けて取り組んでまいります。



2030年の国スポは、津和野町の魅力を町内外に発信する大きなチャンスです。
まず、競技や関連イベントでどのくらいの来町者が見込めるかをデータで把握し、宿泊・飲食・交通などの分野ごとに経済波及効果を算出します。
そのうえで、民間事業者や地域団体と連携し、町全体の受益を最大化する戦略を立てます。
行政職員を含め、必要な人員体制や費用をしっかりと積算し、町に過度な負担をかけず、確実に利益と誇りを生む仕組みを整えます。
たとえば、地元中高生によるボランティア参加、特産品の販売・体験企画、町民が主役のおもてなしプロジェクトなど、住民一人ひとりが関われる形をつくります。
また、イベント後もその熱を継続させるために、
観光・教育・文化・スポーツを結びつけた地域ブランドづくりを進めます。
民間の柔軟な発想と行政の公共性を掛け合わせ、
「津和野はおもしろい、挑戦できる、誇れる町だ」と感じてもらえるような、
持続可能な地域の盛り上げ方を実現していきます。


👔 町政・組織
職員採用について、募集をかけるだけで応募がある時代は終わりました。かつ、町職員という観点でいくと学歴がある=適任ということでも無いと考えます。
今後、津和野町が進めていく町政において適当な職員を採用していく為の策は、どんな事があると考えますか?
補足
若手職員で採用チームを作って、間口を拡げるのが良いかと思いますがいかがでしょう?
候補者からの回答



これまでの町職員の採用は、公正公平な選考が客観的にも保障されることを重視し、ルールを定め行ってまいりました。
一方で社会情勢の変化等により町内のあらゆる業種で人手不足となっており、町役場においても以前と比較して応募が少なくなり、求める採用枠を満たす職員の確保が難しくなっている状況にあります。
人事担当課である総務財政課では、事務職に限らず土木技師や保健師、保育士をはじめとする専門職の応募を促すため、島根県内や山口県、広島県等の学校を訪問のうえPRするなどし、その結果として採用につながる一定の成果は得られているものの、十分とは言えません。
このようなことから、今後の採用にあたっては公正公平な選考が担保されることは大前提に、例えば、現在津和野高校には町内外から生徒が入学されておりますので、卒業後の進路として高校推薦の枠を設けること、あるいは町内から近隣の高校に入学された場合の生徒さんにも推薦枠を広げることなどについて検討する必要性を認めております。
また現在は土木技師の確保に向けて、返還免除を盛り込んだ町独自の奨学金制度を創設したところであり、今後は他の職種についても拡大するかどうかの検討を行うことも視野に入れております。
ご指摘頂いた町若手職員による採用チームの結成については、職員労働組合から既に提案を受けており、私としても職員確保は重要な課題であり歓迎しております。今後、具体的な実践活動に移して行きたいと思っております。
職員の確保は定住対策にもつながるものであり、町内のご家庭へ積極的に募集のPRを行い、子どもさんやお孫さんたちに帰って頂く機会にもつなげてまいります。



これからの時代、募集をかければ応募が集まるわけではありません。どんなビジョンを掲げ、どんな行政をつくっているか——その“あり方”こそが最大の採用戦略だと考えます。「津和野の行政はおもしろい」「挑戦できる」「ここで働きたい」と思ってもらえる組織文化をつくることが第一歩です。
そのために、職員の育成と挑戦できる環境づくりを大きな柱に掲げます。 行政職員一人ひとりに明確な役割と目的意識を持ってもらい、町民とスクラムを組んで新しい価値を生み出す行政のあり方を打ち出していきます。
また、採用段階から、町のビジョンと育成方針を一貫して体現できる採用チームを設けます。年齢や立場に関わらず、職員の中から多様な視点を持つメンバーを選び、町のリアルな魅力や行政の使命を自分たちの言葉で発信していく。SNSや動画などを活用し、「津和野で働くって楽しそう」と感じてもらえるPRを戦略的に進めます。
学歴については、私自身が高卒ということもあり、まったく関係ないと考えています。中卒であっても意欲や感性のある人材は積極的に採用したい。即戦力だけを求めるのではなく、潜在的な能力や地域への想いを持つ人を見いだし、町で育てていくことを大切にします。
挑戦を応援し、失敗を成長の糧とできる風土を行政から生み出す。そうした環境をつくることで、「人が育ち、人を育てる町」としての津和野の魅力を高め、自然と「この町で働きたい」と思ってもらえる行政を実現していきます。


👔 町政・組織
社会教育を通した町づくりをどう考えていますか?
そのための方向性の1つとして、公民館職員の雇用や待遇について改善していく方針があるのかお聞かせ願いたいです。
補足
公民館職員は、地域団体や役場と連携して地域行事を運営したり、地域住民の声を聞きながら地域の人々が集い学ぶ場を開いたりします。
そこには一人ひとりの声を丁寧に聞き、地域住民と信頼関係を築き一緒に地域をつくっていく姿勢が求められます。
地域団体の事務局を公民館が担っていることも多く、各団体について細かく把握し、関連する機関との調整も行います。
地域のみなさんの仕事の都合に合わせると、会議が夜に開催されることも多く、公民館職員は必然的に長時間労働が余儀なくされます。
主事は会計年度任用職員であり、昇給もなく2年ごとの更新が必要になります。公民館長は地域推薦のために、社会的な保障は何もありません。子育て家庭の中で主となって生計を支える場合、公民館職員では不安を感じながら働くことになります。
このままの待遇では、津和野町における社会教育の分野でその専門性を発揮し津和野町に貢献していきたい熱意のある人材が、公民館職員という立場で安心して働くことができません。仕事量やその専門性と給与や待遇が見合っていないと感じる人が多いからです。
津和野町のように小さな地域では、公民館単位の繋がりや地域づくりが地域住民の生活に直結します。
その地域住民の繋がりづくりや活性化を担っている公民館職員に対して、公民館職員自身が安定して安心して働ける労働環境や待遇を望んでいます。
公民館職員がその専門性を発揮しやすい環境をつくっていくことは、0歳児からの人づくり政策を掲げる津和野町において、学校教育以外の津和野町全体の資源を活かして大人も子どもも学び合える町をつくっていくことにもつながると思います。社会教育を通した町づくりをどう考えているのか、そのための方向性の1つとして、公民館職員の雇用や待遇について改善していく方針があるのかお聞かせ願いたいです。
候補者からの回答



ご指摘のように公民館に従事する職員は、地域と行政をはじめ様々な組織を結び、社会教育を推進して地域振興に貢献する大切な役割を担って頂いております。
そうした役割に見合う待遇の改善については、これまで十分ではないと思いますが、それでも少しずつ実施してまいりました。
公民館主事が該当する会計年度任用職員の昇給制度については、令和3年より実施し、毎年昇給する仕組みとしており、期末手当についても同年度より、更に令和5年度からは新たに勤勉手当についても支給しております。
会計年度任用職員は公民館に限らず様々な職種においてそれぞれが重要な役割を担い、誠実に働いて頂き感謝しております。少しずつでも皆さんの待遇改善を図りたいと思い取り組んでおりますが、人件費比率の観点や町財政への影響などを考慮し、組織マネジメントをして行かなければならないこともご理解を頂きたいと思っております。
町内各地域の課題の解決と活性化の取り組みにおいては、約10年前よりまちづくり委員会制度を創設し協働のまちづくりを進めてまいりましたが、再来年からのリスタートを目途として、これまでの運営や活動の検証と今後の在り方について、まずは役場内部のプロジェクトチームを立ち上げて検討を始めたところであり、今後は住民関係者のご意見を聞きながら再構築して行く予定です。
この中で公民館との連携は重要な検討課題と現時点で認識しており、公民館職員の負担軽減と他の会計年度職員との相乗効果が生まれるような活性化策を導き出してまいりたいとも思っております。



教育委員会にいた時も、また地域住民として公民館などと共に活動する中でも、主事の方々の大変さや心痛は、痛いほど感じてきました。
主事に限らず、さまざまな行政機関の中に会計年度任用職員の方々がいて、その待遇や立場の不安定さについて、多くの切実な声を耳にしてきました。
主事は地域の要です。事務的な仕事も多く、さらに世代の異なる地域の方々と丁寧に関わるコミュニケーション能力や、調整力も求められます。これは並大抵のことではありません。
一方で、正規職員からは「うまくやることが仕事だ」と見られがちで、年配の地域の方からは十分に理解や感謝を得にくい立場でもあると感じています。待遇改善はもちろんのこと、定期的な交流や意見交換の場を設け、主事が果たしている役割の価値を地域全体に理解してもらえるようにすることが大切です。
町長として、教育委員会と協力しながら、主事の皆さんが地域のコーディネーターとして誇りを持ち、スキルを高めていけるように、働き方の工夫も進めていきます。
主事の皆さん、本当にいつもありがとうございます。
町民一人として、心から感謝しています。


🏫 教育
津和野町では人口減少や子どもの減少が続いていますが、子育て世帯の定住や転入を促すために、任期の4年間で特に優先する施策を優先順位とともに具体的にお聞かせください。
その施策と優先順位を決めた根拠やデータも併せて教えてください。
補足
定住先を考える時期である未就学の子どもがいる世帯に向けての施策が必要だと考えるから。
候補者からの回答



津和野町では子育て世帯の定住を目的として、保育料の無償化、高校生までの医療費無償化、こども家庭センター来る未の設置、幼児教育コーディネーターの配置、病後児保育の実施、保育園等へのおむつやお米の提供、放課後児童クラブへの昼食提供など、様々な支援事業を実施してまいりました。
一方でこうした事業は全国の多くの自治体が実施しているものでもあり、これらにプラスして本町ならではの特色をもった施策を展開したいとの思いで現在取り組んでいるのが教育の魅力化による教育移住の推進です。
始まりは津和野高校の生徒数の減少による高校存続への危機感から高校の魅力化に取り組んだことによるもので、町内外から多くの生徒を迎えるまでに成果を出してまいりました。
現在はそれを更に発展させるべく、保育園から小中学校、そして高校までを系統立てて、ふるさと教育とキャリア教育を進める0歳児からのひとづくりプログラムによる本町全体としての教育の魅力化を目指しております。
本町はその歴史上において現在に至るまで、社会に貢献し活躍する多くの人材を生み出してまいりました。教育の町・津和野町としての伝統を重んじ、教育の魅力化による人づくりをまちづくりの柱に据えることは、本町が進むべき方向として相応しいものと考えております。
今年度からは、教育ビジョンや津和野高校の普通科改革に歩調を合わせ、IT系誘致企業との連携による更なる教育魅力化の取り組みをスタートさせました。このような動向と合わせ、本町で子どもが教育を受けながら親も一緒に定住し、テレワークにて仕事に従事できる住まいの支援なども行いながら、小さいお子さんをもつ家庭も含めた教育移住を実現してまいりたいと思っております。



私自身、事情があって子どもを連れて津和野に移住しました。母の実家に移ってから数年間は、子どもの将来や仕事を考えると「いずれ都市部に出ることも考えなければ」と思っていました。その中で感じたのは、子育て世帯が“町に応援されている”と実感できることこそ、定住の鍵だということです。
私は、子育て世帯の定住・転入促進のために、次の2つを最優先に進めます。
① 教育・子育て環境のオリジナリティを明確にし、戦略的に発信すること。
津和野町は教育への熱意や自然環境など強みが多い一方で、その魅力が整理・発信されていません。保育園から高校までが連携し、「津和野の教育の魅力とは何か」を共有し、町としての教育ビジョンとキャッチコピーを策定します。「自然・文化・人とのつながりを通して育つ津和野の学び」をブランド化し、定住先を探す未就学児世帯に明確に届けます。
② 経済的な安心を支える仕組みをつくること。
津和野は近隣に大学等がなく町外に出ることになるため教育費がかさみます。津和野での子育てや進学にかかる費用の実態を調査し、専門学校等も含め進学費用をサポートする制度を検討します。また、かかる教育費を踏まえて、子育て世代や保護者の経済的な後押しを含めたライフプラン研修や、オンラインで取得できる資格の受講制度の導入や資格取得費用の補助を進めスキルアップをサポートします。
こうした施策を通じて、「町に応援されている」と感じられる体制をつくり、 成長した子どもたちが将来、思いを返したいと思える—— 人と想いが循環する津和野をこの4年間で実現していきます。


🏫 教育
国による2026年4月からの給食無償化は、子育て世帯の負担軽減に繋がる一方で、『財源の確保』『給食の質の低下』『食育意識の低下』という課題が指摘されています。
津和野町長として、これらの課題に対し、給食無償化を単なる『無料化』で終わらせず、『地域資源を活用した質の高い食育の機会』へと昇華させるため、どのような具体的な解決策を講じていくお考えですか。
特に、地元の農家と連携した地産地消の推進や、給食を通じて食の重要性を伝えるための独自の食育プログラムなど、津和野町ならではの具体的なビジョンをお聞かせください。
補足
津和野町の豊かな自然を活かし、地元の農家と連携したオーガニック給食を目標にしていただきたい。
子どもたちの健全な成長を促す食育を進めるとともに、農業の担い手不足解消にもつながると考えてます。
給食という安定した需要があるため、農家は安心して生産を続けることができ、 子どもたちが地元農産物を通じて食への関心を高めることで、将来的に農業を志すきっかけになります。
さらに、安全で安心な食環境を整えることは、子育て世代にとって大きな魅力となり、移住促進と地域活性化につながる好循環を生み出します。
津和野町が誇る自然環境を活かし、給食を「食育の場」としてまた、「地域づくりの核」として位置づけ、子育て世代にとって魅力ある町づくりをお願いします。
候補者からの回答



私は「食育」のスタートラインが、食という恵みに対して感謝する気持ちを育むことにあり、次の期も町長としての仕事を担わせて頂くならば、そのような観点からまずは給食の残食をテーマとした取り組みを進めてまいりたいとの希望をもっております。
地元産の有機食材であれ、全国から流通した食材であれ、提供されたものが出来るだけ捨てられることなく食する大切さを子どもたちの心に宿して行くことが食育の基本となるとの思いです。
残食のデータを取り、残さず食べてもらえるように子どもたちの嗜好にそった栄養のある美味しいものを作ることは学校給食センターの使命でありますが、同時に子どもたちにもひとつひとつの食材の生産や流通の過程、生産者や調理する人の思いなどに触れる機会を通して、提供された給食を大切にする食育を展開したいと思います。
0歳児からのひとづくりプログラムでは「まち全体が学びの場」と称し、保育園や学校、家庭や地域、そして行政が連携したふるさと教育を展開し、子どもたちから大人までが一緒に学ぶことを土台としております。
その中に食育を取り入れることで残食を減らし、食に感謝する気持ちを子どもはもとより保護者の皆さまにも一緒に育んで頂くことにつながると信じます。
現在、地元農家から給食センターへ食材を供給する実証実験を始めております。有機食材の活用についても幅広い保護者の理解を進める努力が必要とも認めております。食育の学びは、それらの解決へもつながって行くと期待しております。
そして無償化を検討している国に対してもその理念を失うことなく実施して頂くよう機会を捉え訴えてまいりたいと思っております。



食べることは人間の基本だと考えます。そして、その土地でとれたものを、生産する価値や喜びを感じなから、一次産業に従事する人のおもいとともに味わい、育っていくことは、田舎ならではの素晴らしい環境だと思います。
生活が苦しい家庭への支援はもちろん必要である一方で、「質の高い給食」「食材の価値」「生産者の想い」を感じられる給食をないがしろにすることは、持続可能ではありません。
給食センターで地元の野菜やお米を使うには、規制上の大変さがあることは承知しています。しかし、それも農家さんたちと「どうすれば実現できるか?」を一緒に考えていければ、必ず実現できると考えます。
生産者が「この町の未来を支えている」という誇りを持てるように、町としてどのように支えていけるかを本気で考えたいです。
また、必要があれば国レベルでの対策やルール変更を要請していく必要もあると思います。
こうした取り組みは、一次産業の担い手不足の解消にもつながるはずです。


🚖 観光
観光振興計画にとどまらず、町長として2030年のインバウンド戦略をどう描き、どのように実行していきますか?
2030年に向けたインバウンド強化が国の重点施策となる中で、津和野町としては今後どのような観光の方針・戦略をお考えでしょうか?
ローカルな魅力を持つ津和野だからこそ、今後の追い風を活かすためにも、町としての明確なビジョンや方向性を共有できる機会があれば嬉しく思います。
補足
日本政府は2030年に訪日外国人旅行者数6,000万人という大きな目標を掲げています。2024年の時点ですでにその半分以上、約3,687万人が日本を訪れており、これは過去最高だった2019年を上回る数字です。
その中で、いわゆるゴールデンルート(東京・大阪・京都など)ではオーバーツーリズムが課題になっており、今後は地方やローカルな地域への関心が高まってくると予想されています。
津和野は、まさにそうしたニーズに応えられる魅力的な地域です。にもかかわらず、今このタイミングで町として戦略的な取り組みを示さなければ、観光客の選択肢にも入らなくなってしまうのではないかと感じています。
観光に携わり努力を重ねているつもりですが、町としての方針や支援体制があることで、より効果的に津和野の魅力を発信できると思っています。
候補者からの回答



観光の町である津和野町にとってインバウンド対策は重要との認識に立っております。
こうした中、5,6年前より本町のキリスト教殉教者の列聖・列福の動きが注目されるようになり、認定のあかつきには欧米を中心とした世界に対してアピール力をもつ観光資源になるとの期待を寄せております。
一方で認定という事実だけではインバウンドの取り込みにつながるとは考えておらず、効果的な情報発信を行うためのツールの一つとして、世界的なネットワークをもつ外資系ホテルの誘致に取り組んでまいりました。
ホテル誘致については土地貸借契約の締結に至ったものの、物価高の影響を受け施設建設の着工について、相手方が情勢を様子見されているのが現状です。急ぐことなく列聖・列福の進捗と合わせ今後も引き続き誘致活動を継続してまいります。
こうした背景において、インバウンドも含めた本町の観光の方向性について私は「祈り(祈願・願い)」をテーマとした取り組みを進めたいとの思いをもっております。本町には殉教者の歴史をもつ乙女峠とカトリック教会、全国に名の知れた太皷谷稲成神社や国重要文化財鷲原八幡宮、そして多くの古刹があり、また鷺舞や流鏑馬などの神事、津和野踊など祈りや祈願を連想できる伝統行事を有しております。
人はそれぞれに信仰する宗教を持っておられますが、旅先では訪れた寺院や神社などにおいて祈願をいたします。本町が有している様々な財産を組み合わせながら観光の魅力化と情報発信を行い、入込客の増加と滞在時間の延長に結び付けて行きたいと考えております。
紙面の都合上具体的なところまで言及できませんが、現時点で私が考える方向性であり、観光協会や商工会、関係者との共通理解に立つことを前提に取り組みたいと考えております。



私も、津和野は「地区ごとに個性があり、価値がありすぎる町」だと感じています。だからこそ、今後はその魅力を“点”ではなく“面”として発信する戦略が欠かせません。
これまでは、店舗やイベント、サービス単位での発信が中心でした。これからは、町全体で「一つの物語」として発信していく。 たとえば、あるイベントに合わせて関連店舗が一斉に発信したり、自分の店の情報だけでなく、あえて町内の他店や体験プログラムを紹介し合う。さらに、すべての発信にAI翻訳などを活用して英語表記を付けるなど、町民みんなで「世界に伝える津和野」をつくっていきます。
ご指摘の通り、2030年のインバウンド拡大の波に乗り遅れることは、 津和野にとって死活問題です。町としても、観光協会・事業者・地域住民との連携を軸に、「誰が」「どんな発信を」「どんな効果を狙って行うか」を共通認識として整理し、面での取り組みが経済にどう波及するかを数値化して検証していきます。
外部コンサルに頼るのではなく、町民が知恵と経験を出し合って戦略をつくる。そのプロセス自体が人づくりになり、津和野ならではの観光ノウハウとして地域に残る。それが最終的に、「ひとづくり × まちづくり × 経済循環」を実現する、津和野型のインバウンド戦略だと考えています。


🚧 建築予定
津和野町民センターの施設耐震改修に伴う、文化ホール増築の要望が2025年6月の一般質問でありましたが、賛成でしょうか?反対でしょうか?
具体的な理由も併せてお答えください。
候補者からの回答



公共施設の耐震化は国の方針に沿って進めており、特に避難所ともなる防災施設の耐震化は自治体の責任として避けて通れません。
津和野町においてもこれまで、小中学校舎や体育館をはじめとする施設の耐震化を順次進めてきたところであり、津和野町民センターにおいてもようやく着手する時期を迎えております。
こうした中で、耐震化を目的とした整備の方法論の一つとして文化ホール建設の要望を住民組織から頂いたところでありますが、賛成か反対かというよりも実現可能かどうかという判断が私には求められるものであり、その観点において現時点では回答が難しいというお答えになります。
耐震基準を満たす整備を既存施設の改修で実施するのか、あるいは既存施設の全面解体による新築の施設とするのか、一部老朽施設の解体による改修と増築を複合させたものとすべきか、まずは見込まれる概ねの予算規模を算出することから検討して行くことになるかと思います。
合わせて、国からの交付金あるいは補助金等の獲得の可能性についても検討する必要があります。交付金や補助金はそれぞれに対象となる条件が定められており、場合によっては改修よりも新築の方が町独自の財源を軽減する方法にもなり得ることから重要な検討事項となります。その他、施設の維持管理コストも改修、新築、増改築それぞれに比較検討しなければならないと考えております。
そして当然のことながら、住民のご意見も聞きながら最大公約数を事業に反映して行くことが重要と考えており、十分な意見交換の出来る機会を設けながら検討を行い、最終的には住民代表である町議会の判断を仰ぎたいと思っております。



文化ホールの増築が、この町の未来にどんな可能性を生み出すのかを明確に示せるものであれば、投資する意義はあると考えます。
しかし、単に「あると良い」「補助金が今使えるから」という理由だけで建てるのなら、私は反対です。
それでは、将来の負担や“負の遺産”を町に残すことになりかねません。
山村開発センターの代替施設も同様ですが、
建物をつくること自体が目的ではなく、その施設がどのような価値を生み出し、どんな人の学びや交流を支えるのかを明確にする必要があります。
もし文化ホールを検討するなら、
子どもから高齢者まで、町民の誰もが「この施設があることで町が豊かになる」と納得できる根拠とビジョンを示したうえで、丁寧に議論を重ねるべきだと考えます。


❤️ 福祉
津和野町内どの地域でも、高齢者の移動手段(買い物、通院、地域の交流の場への参加など)について、現在の公共交通手段では足りていない(朝のバスで移動をしても、帰りのバスが夕方までない)と声が上がっている現状です。
これからの高齢者の移動手段の施策とその施策の根拠を説明してください。また、その施策は何年後までに実現しますか?
補足
高齢者のみならず、子ども達の習い事の送迎、通学も困っている親御さんがいることを聞いています。町民全体の課題でもあると思います。
候補者からの回答



過疎高齢化が進む中、高齢者の移動手段の確保は重要でありながら、町営バス等の公共交通システムが皆さまの利便性を十分に満たしている状況にはないことを認識しております。
一方で、現行の町営バスの運行には年間約6千万円を投じており、これ以上の便数の拡充等には慎重を期する必要があるとも思っております。
こうした中で、交通弱者である高齢者の悩みや課題を解決する一助になる対策も検討してきたところであり、現在は医療法人橘井堂の皆さまのご協力により木部地区及び須川地区での巡回診療を実施しております。
また、日原地区のスーパー廃業に伴う買い物難民の発生抑止を目的として商業施設を建設いたしましたが、そこを拠点として現在は、津和野町全体の地域に移動販売を行うシステムを構築し、高齢者が移動を極力伴わない生活を支える取り組みも実現しております。
尚、現在の町営バスの運行時間においては、お昼前後と夜間において空白の時間帯が存在しており、住民の方々からその時間帯の空白解消による利便性の向上を期待する声を多くお聞きしております。
JR山口線の最終便運行後における高校生の部活動後の帰宅や社会人の懇親会後の帰宅の需要を鑑み、まずはバスによる夜間運行の実証実験を国の補助金を活用し実施しております。
実験結果をもとに、民間事業者による自立した運行継続を期待するとともに、もう一つの課題であるお昼前後の空白解消による解決にも同様に取り組んで行きたいとの思い持っております。
小中高生の通学については、入学と卒業により乗車希望者の事情が毎年のごとく変遷しますので、出来るだけ柔軟に対応できるよう努めてまいります。



高齢者の移動手段については、地域の互助による仕組み化を目指します。
国の制度や安全面のルールなど、簡単ではない課題も多いですが、津和野に限らず全国共通の課題であり、私たち現役世代の新しい発想と工夫が問われている分野だと感じています。
具体的には、地域の団体や住民が協力して運行する「地域乗合カー」や「送迎ボランティア制度」の導入を検討します。
また、町内のタクシー・介護事業者・学校・子育て世帯などが連携し、高齢者の通院・買い物支援にとどまらず、子どもの習い事や通学支援にも活用できる“助け合いによる移動の仕組み(共助型モビリティ)”をつくります。これにより、交通弱者を個別に支援するのではなく、町民全体で支え合う交通文化を根づかせたいと考えています。
町内ですでに助け合いの移動手段を実施している地区もあります。その取り組みの現状を踏まえて、まずは既存の地区で実証運行を始め、3年以内のモデル地区稼働、5年以内の町内展開を目指します。
行政が制度を整えるだけでなく、地域が「自分たちで支え合える仕組み」をともにつくることこそが、これからの津和野のまちの強さにつながると信じています。


🍀 農業・林業
清流高津川は、町民の生活を支える大切な水源であり、流域の豊かな自然環境を育んでいます。しかし、放置された人工林は、保水力の低下や土砂の流出を引き起こすだけでなく、鳥獣害の被害を拡大させる一因にもなっています。
高津川の清流を守るため、「災害に強く、多様性のある水源の森」をどのように育て、野生動物との「住み分け」を促す森林整備をどのように進めていくお考えですか?
具体的な取り組みや計画についてお聞かせください。
補足
以下の3つの取り組みを連携させて進めていただきたいです。
①町内・町外所有者への働きかけ強化
山林の現状や管理の重要性を伝え、整備への関心を高めるための情報提供を強化してください。
②管理代行システムの構築
所有者に代わって森林を管理する仕組み(例:受託制度、信託制度)を確立し、管理の継続性を確保してください。
③所有権の集約・再構築
放置が続く山林を行政などが買い取る制度や、一元管理する「森林バンク」のような仕組みを創設し、効率的な森林整備を可能にしてください。
これらの取り組みを通じて、山林所有者の所在地に関わらず、計画的かつ継続的な森林整備を推進し、高津川の清流を未来に引き継いでいくことを強く要望します。
候補者からの回答



津和野町では、平成28年に美しい森林条例を制定し、その中に盛り込まれている森林憲章を理念として森林・林業施策を展開しております。
これまでの具体的な取り組みは、地域おこし協力隊制度を活用しての自伐型林家の育成、山の宝でもう一杯事業による林地残材の活用、航空レーザー測量によるデータ活用、木質バイオマスガス化発電事業の導入などが挙げられ、十分とは言えないながらも他自治体と比較しても先進的に事業を推進してきたと考えております。
「補足」でご指摘頂いた3つの事項は今後の森林・林業施策を推進して行く上で非常に重要なことと共通認識に立っております。平成31年からは森林経営管理法が施行されており、林業の成長産業化と森林資源の適切な管理の両立を図るため、森林経営管理に関する制度化がなされました。
これを受けて、市町村が行う「森林経営管理制度」の取り組みを支援する組織として森林経営推進センターが(一社)島根県森林協会の中に設立されており、本年7月から私が当協会の会長に就任しております。今後、当センターと連携を密にした取り組みを進めながら、ご指摘の事項について実現してまいりたいと思っております。
また令和6年度より森林環境税が始まっておりますが、本町には森林環境譲与税として毎年5千万円強が交付される計画となっており、森林整備等の貴重な財源として有効活用してまいります。
合わせて現在、町有林のJ-クレジット制度の活用による財源確保にも取り組んでおり、間もなく良いご報告が出来るものと思っております、その実績を民有林へも拡大することによって、津和野町森林憲章を具現化する美しい森林づくりへとつなげて行くことができると期待しております。



清流高津川が「清流日本一」と称されるのは、津和野の森林のおかげです。全国でも数少ない“ダムのない一級河川”でありながら、何度も「水質が最も良好な河川」に選ばれています。それは、町の約9割を占める森林が豊かな水を育んでいるからです。
一方で、この「9割」という数字は課題とも深く関係します。放置された人工林は保水力を失い、土砂災害のリスクを高めています。また、餌の少ない山から野生動物が人里へ下りてくることで、鳥獣害も拡大しています。
森林整備を進めるには、所有者の不在や高齢化、境界線の不明確さなど現実的な課題があります。そのため、単なる「働きかけの強化」だけでなく、災害リスクや搬出の容易さなどから優先順位を明確にし、段階的かつ計画的に整備を進めていきます。
また、野生動物との“住み分け”については、山の中に動物が安心して食べ物を得られる環境を整えることも一つの方法です。農林関係者の知恵を生かし、長期的な視点で「共生の森づくり」を進めます。
さらに、津和野町がどのように森林と向き合い、誰がその現場で努力しているのか――その姿を発信することも重要です。「津和野がどうやって森を守り、水を守ってきたのか」を戦略的にPRし、林業に関わる人を増やし、教育・観光・まちづくりにもつなげていきます。
清流を守ることは森を守ること。森を守ることは津和野の未来を守ること。この循環を大切にしながら、「高津川流域の森」を次の世代へ確実に引き継いでいきます。


🍀 農業・林業
農業の担い手不足は、今後更に加速すると思われます。
現状の農業体験事業を都会にPRするだけでは、解決に至らないのではないでしょうか?
その他にどんな対策を講じていくつもりでしょうか?
補足
観光や教育、福祉といった他分野との連携で新たな対策を模索することも考えてほしいです。
候補者からの回答



津和野町の新規就農支援は他の市町村と比較しても手厚いと自負しておりますが、体験であれ本格就農であれ、生産技術や経営環境など厳しい現実に直面した時に対するフォローアップが定着への重要な要因になると考えております。
こうしたことから町内で自立されている先輩農家が新規就農者に対して生産のアドバイスや生活全般を含めた悩み事への対応をして頂く仕組みづくりを行うことが重要と考え、対応される先輩農家への賃金支払いや指導時における経費助成を行う制度を今年度から始めたところであります。
また、津和野町特定地域づくり事業協同組合が組織されており、社会保障が確保された中で農業を学ぶ仕組みづくりも構築しており、こうした取り組みもPRしながら就農による担い手の確保につなげてまいりたいと考えます。
町内飲食店や福祉施設、給食等との連携にも引き続き取り組んでまいりますが、文京区との共同事業であるクラウドファンディングによる町内農産物の生産及び販売支援、ふるさと納税返礼品への活用など、地産地消と地産都消の両面からアイディアを実現してまいります。
そのためにも消費者に愛される農産物の生産が重要でありますので、就農者へのきめ細かい技術指導等にもJAや農業改良普及員との連携を密にしてまいります。
また、農業の基盤整備も行政の重要な役割であり、これまでも町内各地における圃場整備の国等への働きかけと町負担分の財源確保、農機具の更新等に関わる支援など、厳しい財政状況の中でも地域や農家の皆さまの要望に応えるため、財政をやりくりし実施してまいりました。今後もご期待に応えられるよう更なる行財政改革を行って財源の確保に努め、担い手の確保へとつなげてまいります。



農業の担い手不足は、津和野でも最も深刻な課題の一つです。単に都市部に向けて農業体験をPRするだけでは、根本的な解決にはつながりません。これからは、農業を生業(なりわい)として支える人をどう増やすか、どう支えるかに焦点を当てます。
私は、農業を「産業」としてだけでなく、津和野らしい暮らし方そのものとして再定義していきます。 都会と対比したときにこそ見える、“自分の手で食をつくり、季節を感じ、人と支え合う”という豊かさを、津和野の価値として押し出します。
まず、教育・観光・福祉の3分野を横断して農業と結びつけます。
◎教育では、子どもや若者が地域農業に関わる機会を増やし、学校・地域・企業が連携して、将来のUターン人材を育てます。
◎ 観光では、体験で終わらない「継続参加型の農業ツーリズム」を推進し、関係人口を担い手候補へと育てます。
◎ 福祉では、高齢者や障がいのある方が農業を通じて社会参加できる仕組みをつくり、 “農業しながら元気に暮らせるコミュニティ”を各地に広げます。
さらに、農業機械の導入や効率的な生産技術への助成を強化し、狭い土地でも収益を上げられる“稼げる農業”を支援します。空き農地を一元化して公開し、小規模から始められる「半農型の暮らし方」や副業的就農も後押しします。
こうした取り組みを通じて、「農で暮らせる」「農に関われる」人を増やし、津和野の農業を地域を支える文化と暮らしの柱へと再生していきます。10年先を見据え、持続可能な“農のまち津和野”を町民とともに築いていきます。


🏢 インフラ
木質バイオマスガス化発電の今後の展開について考えを教えてください。
補足
バイオマスガス化発電所が津和野町にあることは脱炭素化や森林活用において重要であると感じています。
しかしながら、現在の発電所は民間の経営となっているため、発電や売電において津和野町が関与しているわけではないと思います。
昨今のエネルギー価格の高騰や頻発する自然災害を考えると、エネルギーの自給ができる街というのは非常に強みになると考えています。
そこで、今後は町が発電や売電にも関与し、例えば自営線で公共施設や近隣住宅へ電気を供給するなどの体制を整えていくこともできるのではないでしょうか。
上記に限らず今後の展開についてのお考えがありましたらお聞かせください。
候補者からの回答



津和野町の木質バイオマスガス化発電事業は、平成25年に「高津川流域木質バイオマス活用調査検討協議会」を立ち上げ、森林組合や素材生産業者、森林管理署、島根県などとともに何度も協議を重ねた上で、民間の津和野フォレストエナジーによって立ち上がったものであり、直接経営にタッチしてはいないものの、町としても原料供給のためのチップヤードを設置するなど、深い関りを持っております。
令和4年には津和野町ゼロカーボンシティ宣言を行うとともに、本町の脱炭素社会の実現に向けた再生可能エネルギー導入のための具体的な取り組みの方向性を示す津和野町地域再エネ導入戦略「津和野町における森里川海連環ゼロカーボン事業」を策定いたしました。
この戦略の中で、木質バイオマス発電と付随する熱や残渣物資(バイオチャー等)の活用、今後の発電施設導入の可能性等とともに、新しい地域電力会社の設立によるエネルギーの地産地消と売電の将来像などを盛り込んでおります。当戦略は津和野町のホームページ内でも掲載しておりますので、ご関心があれば検索の上ご一読ください。
一方で、戦略を実行に移すにあたっては、財源の確保の問題や日進月歩で技術革新がなされている機器への対策をはじめ状況の変化に柔軟に対応する必要性を認めております。実際に現在実施している道の駅なごみの里の老朽化に伴う省エネと温室効果ガス排出量の大幅削減を目的とした改修では、木質バイオマスガス化発電施設の導入を見送り、木質チップボイラーの更新へと変更し実施する予定です。
今後も策定した戦略を尊重しながらも、社会情勢の変化により効率的かつ効果的な見直しを図りますが、本町の再エネの核となるのは豊富な森林資源の活用を基本とした木質バイオマスガス化発電であることは言うまでもありません。



「エネルギーが自給できる町」、「森林資源が循環する町」というのは、町の90%以上が森林である津和野町が目指すべき姿だと私も考えます。
行政が積極的に関わり、津和野フォレストエナジー合同会社と協議の上で、町にとっても運営会社にとっても良い方向性を模索したいところです。
ただ、発電用のチップにするためにどんどん木を伐っていってしまうと良質な森が保てなくなるという声も聞こえます。持続可能な発電の仕組みづくりは関係者で熟慮する必要があるだろうと思っています。
バイオマスガス発電所は津和野の価値を高める財産であることは間違いありません。活かしきる方法を運営会社と林業に関わる皆さんと行政とで見出したいと思います。
感想をぽちっと!
- いいね 👍7
- 初めて知った 😄0
- う〜ん 😒2
- それってどうなんだろう? 🤨0
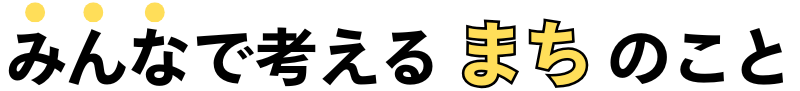
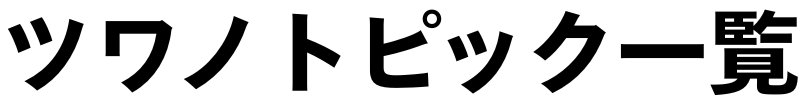

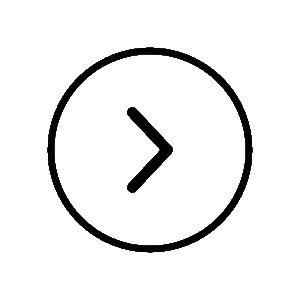
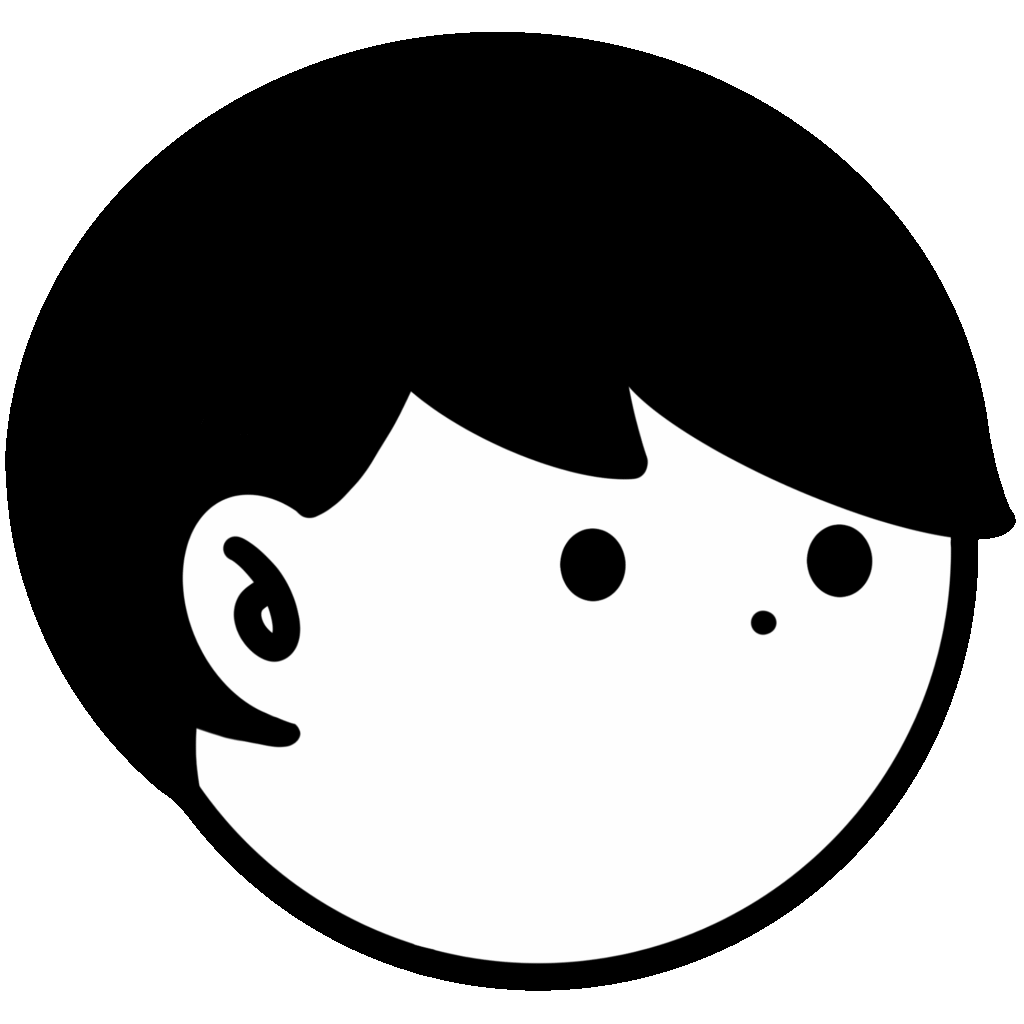
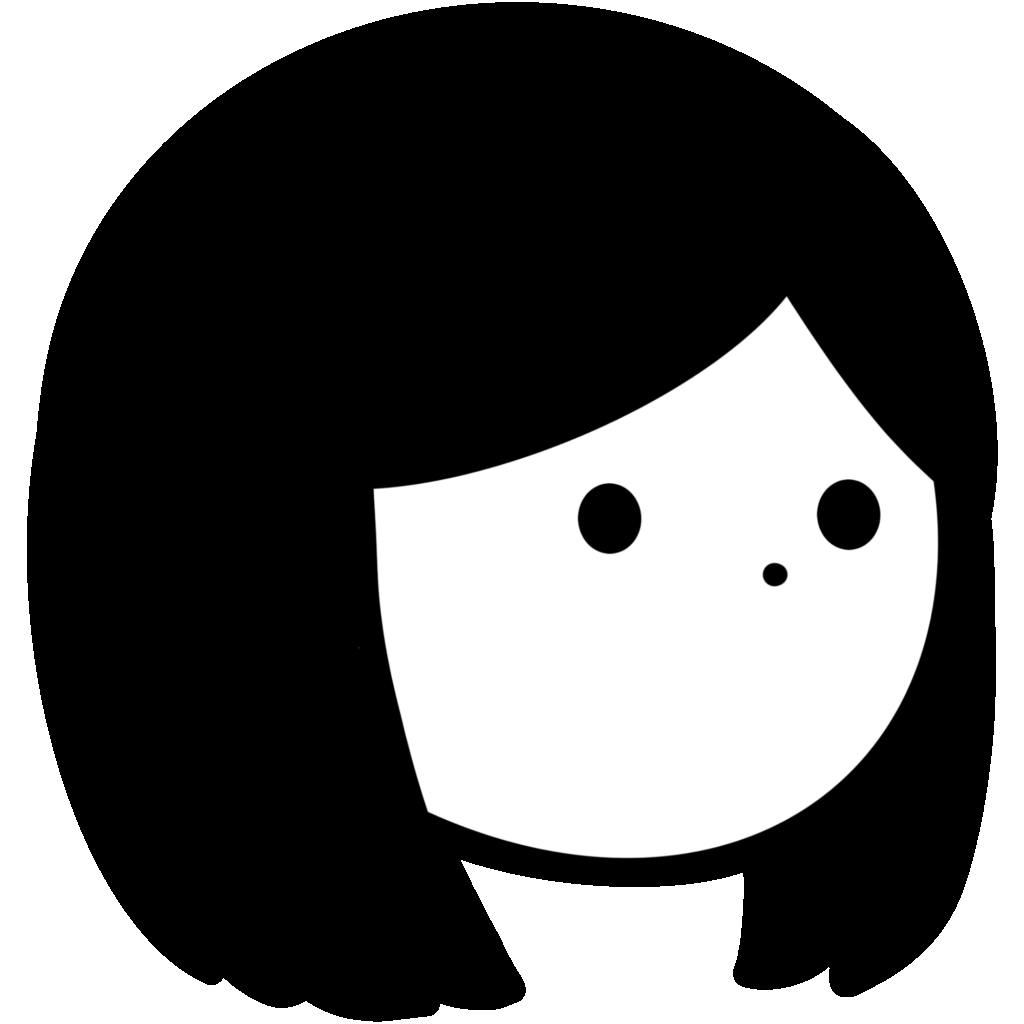
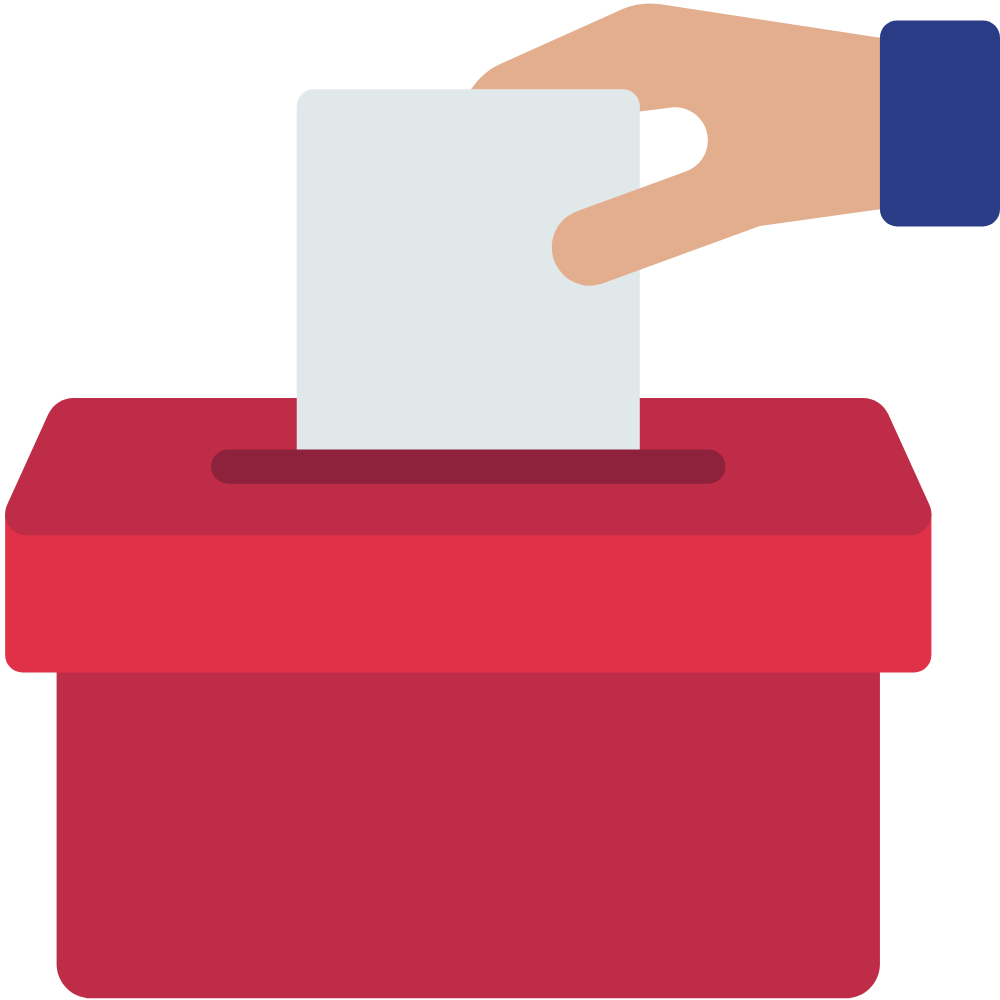
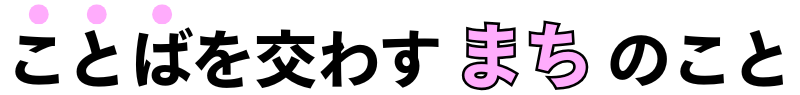
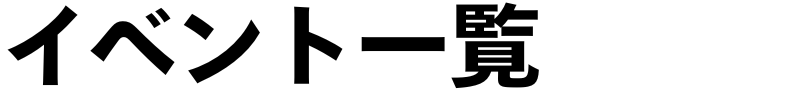

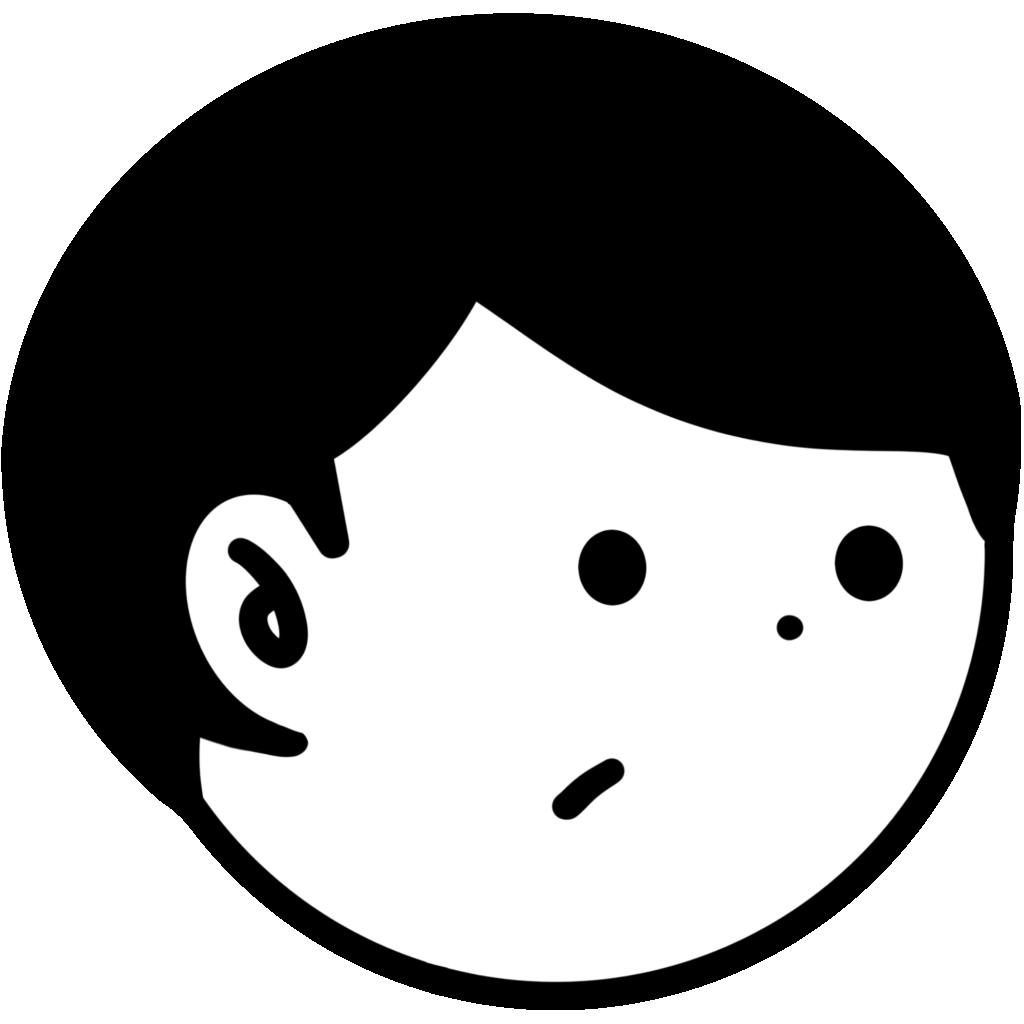









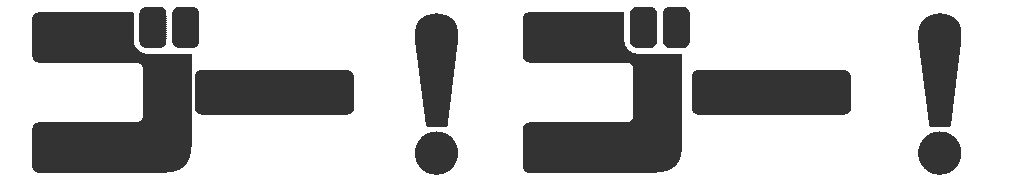

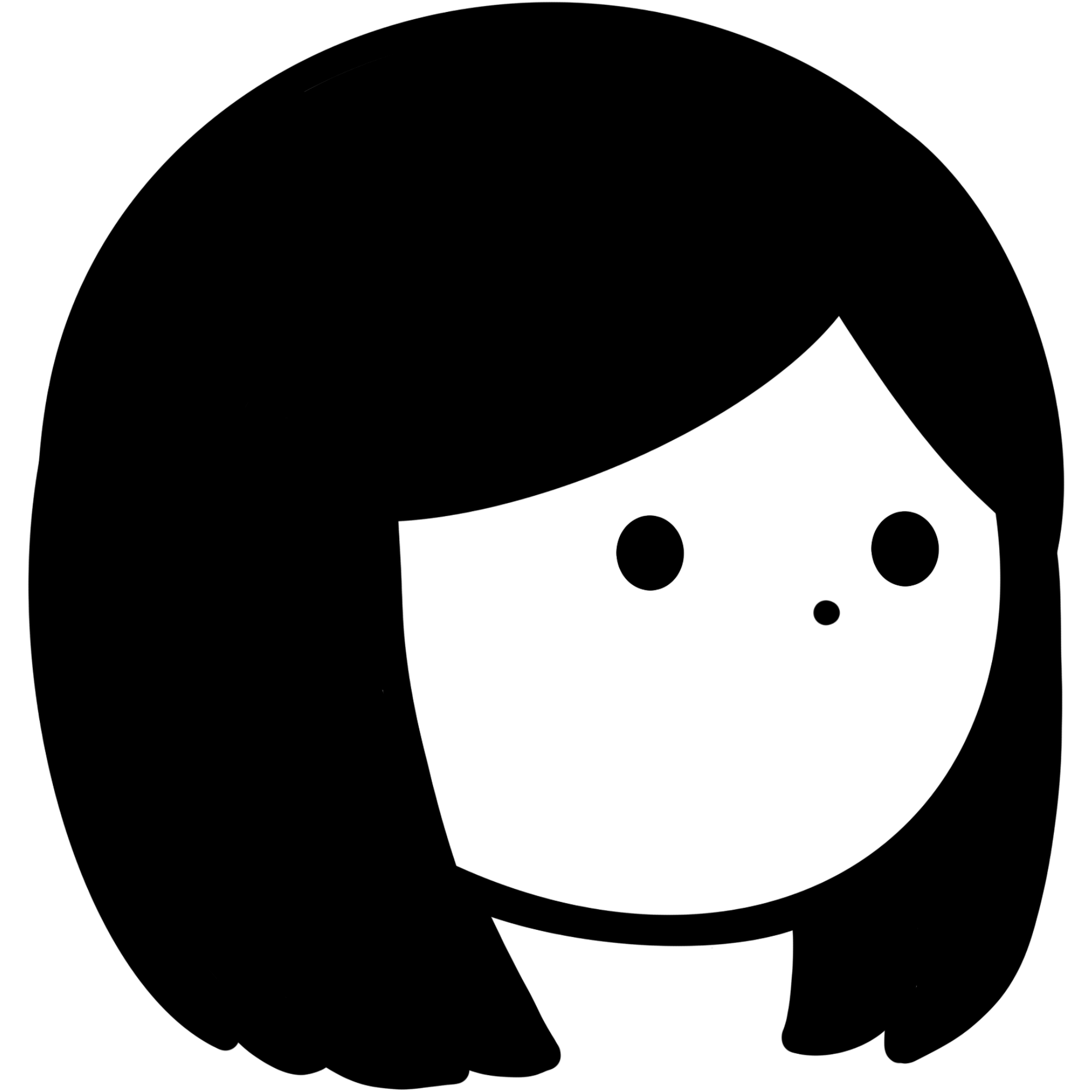








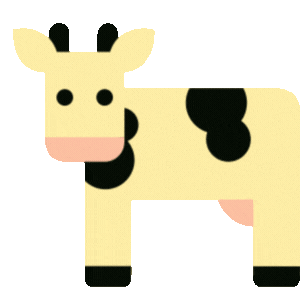
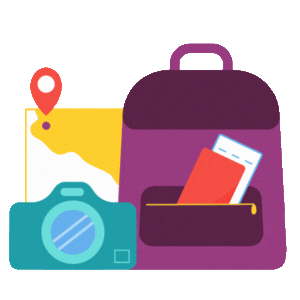

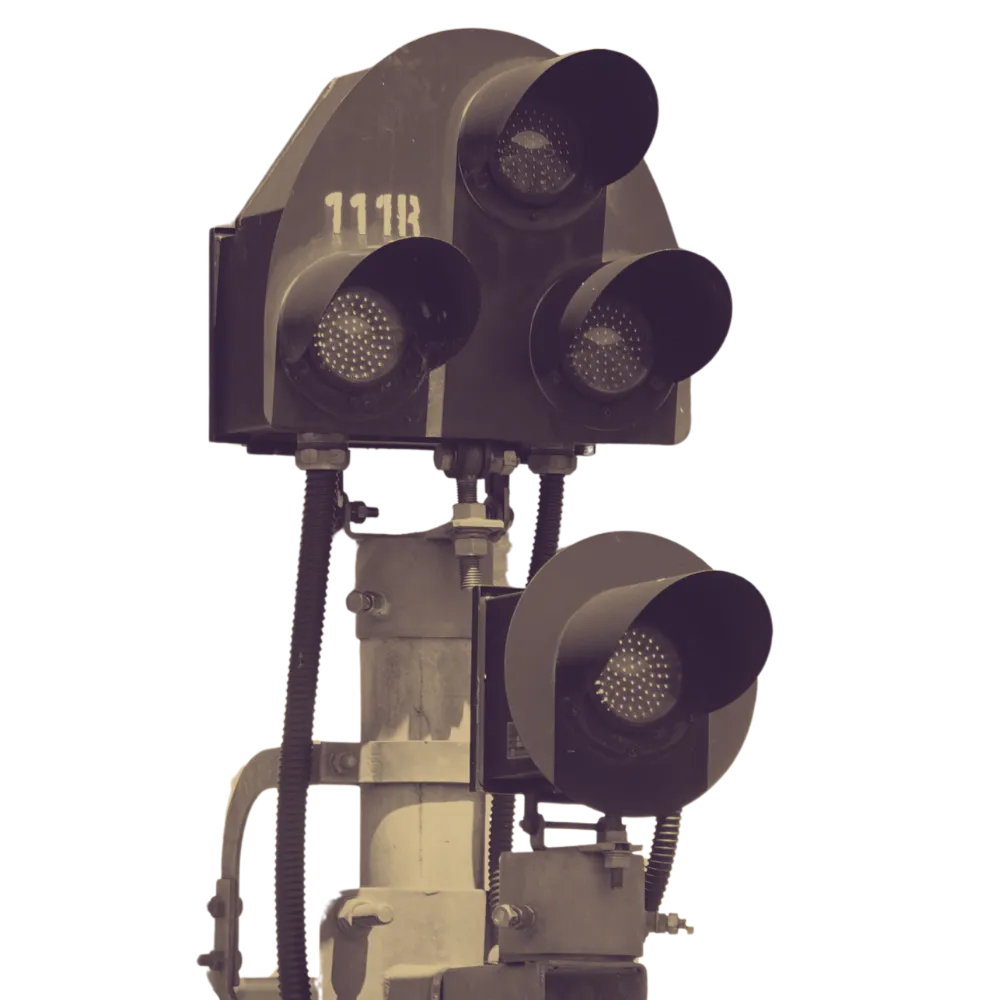



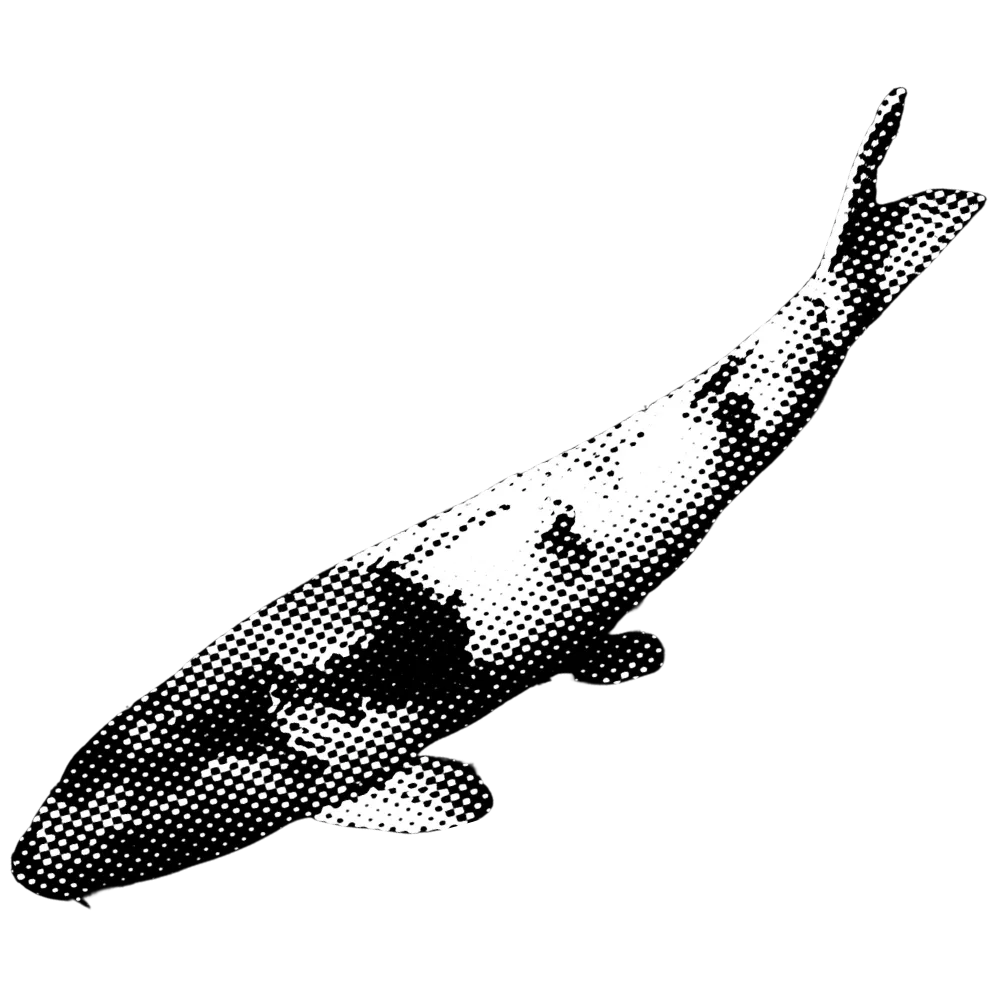


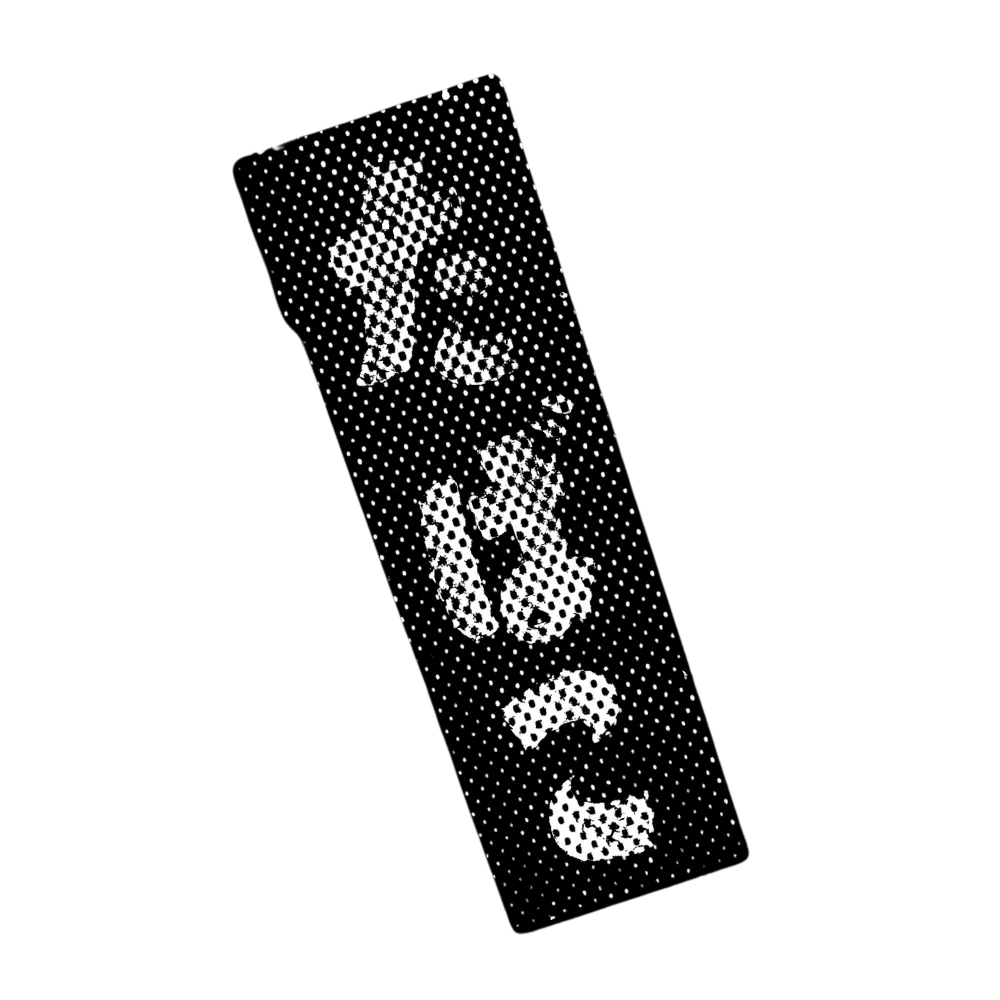




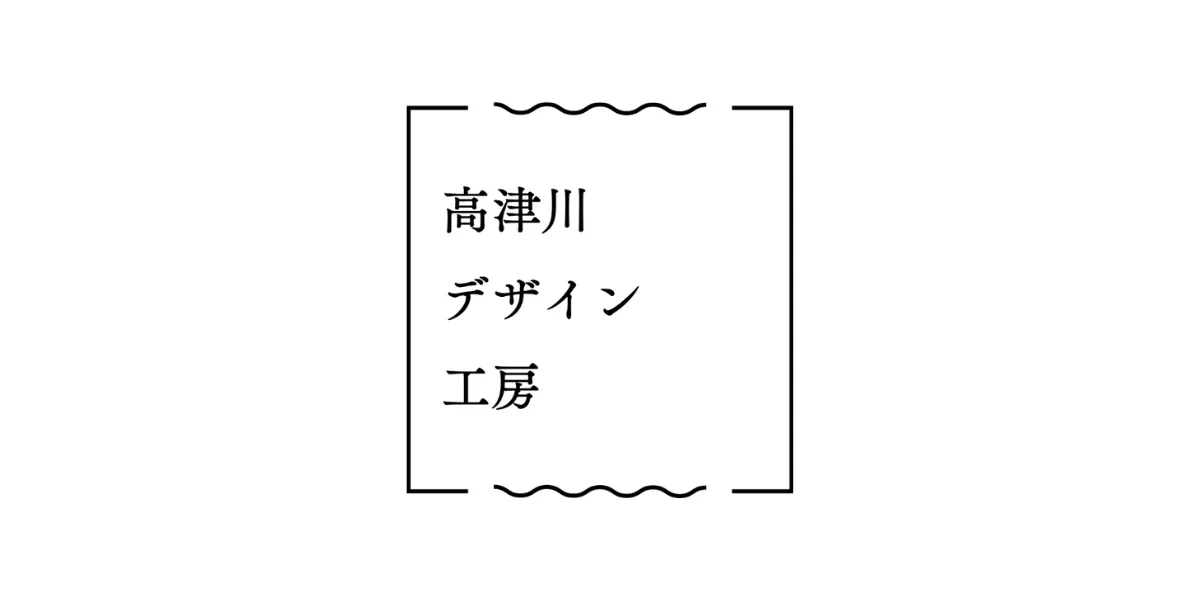


コメント
※いただいたコメントは運営で確認後に公開します。